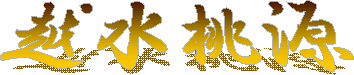勝安房と小栗上野 - 幕臣として - ― 2022年09月16日 17:03

『明治維新運動人物考』田中惣五郎 著
(一八七ー一九八頁)
九 勝安房と小栗上野 - 幕臣として - 2022.09.16
一
勝と小栗を對比して、その本質を論ずることがちかごろあちこちで行はれて居るやうである。昭和維新のかけ聲の賑かなこのごろ、この二人の行き方を再検討することは、決して無意義ではなからう。それ戰術として、節操問題として、時代の見通しの問題として、どの角度から見ても、興味あるテーマである。況んや、やゝもすれば、從来の維新史が薩長的立場からのみしばしば價値判斷を強制して居ると見られて居る以上、その點から考へても、この比較はとりあげられてよいやうに思はれる。
二
二人の思想の端的な現れは、その郡縣論において見られる。慶應二年、幕府が征長の軍を大阪まで進發させて、將軍親征の大がゝりな計畫を賞行したのであるが、財政つゞかず、士気振はず、加へて國際勢力の壓迫と、國内反對勢力の征長反對にあつて、幕閣はほとんど立往生の態であつた。その國内的反對勢力の先頭を承つて居たのが、大久保利通を中心とする薩藩であり、大久保は、公然と征長の道ならぬことを説いて、反對意見書を老中板倉勝靜に呈したであつた。この反對意見書は、いろいろと裏面工作によつて撤回せしめようとしたのであるが、成功せず、やむなく、薩軍の西郷らと善い勝海舟を起用せざるを得なくなつたのであつた。二年前の元治元年、八一八事變の改革派彈壓の餘威をかりて、その一黨と交通して居たと見られる神戸海軍操練所長の勝までを、一氣に壓迫して、江戸へ呼戻して蟄居を命じてしまつたのである。
この復活する勝に對して、小栗の説いたのが、有名な封建から郡縣への意見であつたのである。開國起源によると、
此時顯要官吏、平素余と快からざる者、余を見て愕然たらざるはなく、小栗上野其他兩三名、余を引いて別室到り竊かに議して日く、君今坂地より降命あり、必ず要路の議に與からん。知るが如く今危急の際也 。
政府佛蘭西に金幣幾許軍艦六隻を求む。到着次第一時に長を追討すべし。薩も亦其時宜に依りて是を討ぜむ、然して後、邦内に口を容るゝの大諸侯なし。更に其勢に乘じ悉く削小して郡縣の制を定めんとす。是れ尤も秘密の議既に大凡決定せり。君定めて同意を表するならむ。若し然らむには猶上坂して説く所あるべきなりと。
余今論じて時日を消するの益なく害あるを察して口を開かず。唯之を聞くのみ。後大坂に至つて板倉伊賀に閲す。且つ關東の審議如何を問はる。予謹んで答へ云ふ。郡縣の議は、萬國交際起るに當つて、當然の議なるべし。今我が徳川家、邦家萬世の爲めに諸侯を削小し、自ら政權を持して天下に號令せんとするは、大いに不可なるべし。眞に邦家の御爲めを以て此大事業を成さんと欲せば、先づ自ら倒れ、自ら削小して顧みず、賢を撰み能を擧げ.誠心誠意天下に愧づる事なき地位に立ち、然る後成すべきなり……」
この郡縣論の理解から見ると、小栗は、斷然勝の敵手ではない。郡縣制は、封建制の倒れた後にはじめて確立すもものであつて、「先づ自ら倒れよ」といふ勝の認識が正しいことはいふまでもなからう。しかるに小栗の理解する郡縣論といふのは薩長の如き反勢力を打倒したその上で、諸鍵を削小することをさすらしいのである。そして、薩がなくなり、長がなくなり、諸侯から削りとつた土地と人民をしからばどうしようとするのであらうか。前後の語勢から推して、それは當然徳川家に歸するものらしいが、だとすると、これは幕府を強化する以外の何ものでもなく、これをしも郡縣論とと考へたのだとしたら、その無理解に驚くのである。
もしまた全國を平定して後、徐ろに郡縣制を布くの意圖を藏したら、それは勝のとつた態度と五十歩百歩の相違でしかなく、徳川氏を自らの手で最も巧みに葬る以外方法はなかつたであらうと思はれる。しかし、反對勢力の蹶起なくして.或日突如として郡縣に變るなどゝいふことは、いさゝかでも歴史のあとを眺めた人の肯んじえないところであらう。
人は慶喜の大政奉還を以て、恭順の證とし、郡縣の第一歩と考へるかも知れぬが、形式的の大政奉還ならば、すでに慶應元年に行はれて居たのである。否、文久三年の將軍家茂の上洛が、その先驅とさへ見られるのである。すたはち、尊王攘夷の全國的氣運に押された幕府は、やむなく莫大の上洛費を乏しい財政の中から工面して、京都にいたつて、天子の御前において政を議したのである。形式的なものなら、この時すでに大政を奉還したともいへるのである。
しかも、幕府としては、反幕の氣勢がもり上つて、やがて倒幕に發展せんとする氣勢に脅え、かつは幕府の政權そのものを朝廷に歸し奉ることがかへつて政治運行の方法としては賢明なものであることを、慶應三年の兵庫開港問題の時知つたはずである。すなはち、事府の單獨意見で開港したからこそ全國攘夷の怨みの的となつたのである。そのくせ、八百萬石の威力を有する徳川の實力は、議論の際は斷然他を壓しうるのであるから、名を棄て實をとる方法としては、これに越したものはないのである。
筆者は決して慶喜がさうした意圖の下に大政を奉還したとは斷じたくないのである。事實、目先の見える弱い氣の型の、しかも將軍就任までは、朝廷と幕府の間に立つて緩衝地帶の立場に居た慶喜としては、かなり純粋の氣持で奉還したらうと思ふ。が、同時に、この易きにつく方法として形式的大政を易々として返上したであらうことも、返上前後の慶喜の動きと返上のし方から推察できるのである。否、その後の實質的返上にあたつて、猛然反噬して來たことによつて一層その意圖が明らかにされる。
つまり、徳川氏のもつ大政とは、八百萬石の土地と旗本八萬騎の武力から生まれたものであつて、その點では、薩摩とも、長州川とも。何らの差違はないはずである。だから、この力によつて得た大政を返上するといふことは納土までいつて、はじめて眞の大權返上となりうるのであらう。
徳川の臣下中眞に見透しの利く大量の人物かあつてこそ形式的大權と同時に、實質的の版籍をも奉還し、全國の藩の魁をなして、他藩の版籍までも止むなく返還せざるを得なくさせたら、これこそ素ばらしい頭惱の持主たりえたらうし、徳川のためにもなりえたであらうと思はれる。身を捨てゝた敵の薩長までもろともに同じ運命に立たしめるのである。
ところが、徳川のためを考へてこの擧に出た土佐藩の山内容堂も、その臣後藤象二郎も、はじめから徳川を主座として、天皇を擁した政治をのみ意圖して居たゝため、薩長の討幕によき口餌を與へてしまつたのである。勝の 「自ら掴れよ」といふ意味は、いづれとも推測しがたいが.これは後藤より一歩進んだものであらうことだけはたしかである。
ところが、小栗となると、徳川中心郡縣諭の持主であるだけに、薩長を動かして居る新時代的なものに對しては完全に盲目であり、たゞ薩長憎さと徳川第一主義の點から、猛烈に大政奉還と、これにつゞく辭官納土の要求に反發し、強硬に一戰主張したものである。もちろん、薩長が辭官納土をみずからせずして、徳川にのみ迫るのは、一應の非理であらう。しかし、三百年間政權の地位にあつた徳川としでは、完全に政權の地位から占め出されて居た薩長ののこの抗議に對しては一先づ聞くべき立場にあつたのである。しかも、明らかに朝廷の意志を體したりとする薩長に對して一戰以外策がないといふのは、あまりにも無策であらう。小栗は、盛んに戊辰の役の戰の無策を論じて居るが、小栗はそれ以上に大局的に無策であつたと攻撃されたら、何と答へるであらうか.斯かる無策の出兵をするといふことが、そもそも倒幕前夜の現象なのであり.小栗の無策も、その不可避的な現象と見れば見られぬこともなからう。第一に二倍に餘る會津桑名の兵が薩長の寡兵うち破られたといふことが、桐の一葉に秋を知る現象であり、よし小栗の巧緻な戰闘枝術を以てしても、新時代の武器と兵法に身を鎧つたいはゆる官軍に抗し得たかは疑問であらう。
勝が、小栗を評して、眼識局小にして、あまり學問の無かりし人といつて居り、これに異議をさしはさむ人もあるが、事實蘭學によつて鍛へられた勝の頭惱から見たら、小栗ならずとも、當時の幕閣首惱部のすべてがしかく見えたであらうととは、否みえないであらう。小栗も勝と同じ船で米國に渡り彼地浹を見て來たのであり、軍事にも産業にも一見識を持つていろいろの新施設を行つたことは事實であらうが、それとて識見や經驗のある下僚同僚等の力をかりぬとは斷定しえないのである。そこへ行くと、勝の方は、むしろ智慧を貸す方であつた、決して借りる側の人物ではない。
若し、二三の人だけで相談したりした揚合は、その郡縣論のごとく見當違ひの判斷をずるらしいのである。つまり、この郡縣論は、勝と小栗の思想と知識を知る上において、好箇の材料であると考へられる。
三
勝の臣節については、福澤諭吉の痩我慢説以來、あまり香ばしくないことになつて居る。これに反して、小栗は、むごい死に方こそしたものゝ徳川に殉じた一個の忠節の臣として賞せられて居るのであるが、こゝにも色々と問題はありうると思はれる。
臣節とは何ぞやといふことは、具體的な場合において、中々にむづかしい問題であらう。乃木將軍の殉死も、乃木將軍の歴史を知つてはじめて諒承と讃嘆の聲を發しうるのであつて、だれでもやつてよい行爲でないことは、けだし當然であらう。だから、徳川の爲に死ぬとか戰ふとかいふことだけが、臣節をつくすことだと考へたら、とんでもたい誤謬に陥るのである。
幕府か倒れるものであることは、達識の士はすでに知るところであり、慶喜將軍自身すらこれを知つて先づ大政奉還と稱する外濠を埋めたのである。此場合、あくまで大政奉還を拒んで、若し慶喜將軍がこれに從はざれ これを葬つて他の人を將軍に据えても、將軍の存在を維持繼續することが大義であるといふ場合は、慶喜を殺すことが忠義となりうることもないではなからう。しかし天下の大勢は、天朝にすべてを歸結せしむべきであるといふ傾向に滔々としてなりつゝあるのである。そして、曲りなりにもこれに慶喜が從はうとして居る際に、この勢いに抗して、この勢とあくまで一戰することを主張するものがありとしたら、その人は、時代に盲目であるか臣節を心得ぬ人として譏られるであらう。
なる程、薩長の人々は、あるひは官軍の名あつて實なきものも多かつたであらうが、人間の行爲は、官軍であるからといつて、截然と賊軍と異なる程の立派な個人になり變ることは出來るものではない。そこには不完全な人間の集合體があるだけであらう。しかし、彼等の爲さんとすることと、その目指す方向とが、官軍的でありとしたら、これは恕すべきものであらう。その個々の行爲を論じて責めることばかりして居つたら、すべては否定されざるを得ないことになる。
そして、當時の官軍の立場はしかるが如きものであり、これに對しても、慶喜は恭順を専一とすることを聲明して居るのである。だとしたらこの場合、慶喜の意志と、時勢の前に屈して、せめて徳川氏が有利な立場に立ち得るやうに取計らうべきが臣節ではなからうか。
徳川氏のために、潔く一戰を交へることは、快は快であらうが、これはむしろ相手の術中に陥つて、すべてを破滅せしめることであらう。征東軍の参謀長西郷は、出發前において徹底的討伐を大久保に申し送つて居る。これに對して一戰したとしたら徳川の宗廟は完全に破壊されることは論を俟たない。一戰して勝つと信ずるが如きは、慶喜の征長戰同樣認識不足も甚だしい。勝つものなら、伏見鳥羽の戰で勝つてゐるはずである。戰略はとにかくとして、辭官納地問題に憤慨しきつた幕兵の最強藩の會津を中堅とした大軍でありながら、二分の一、三分の一とさへいはれる官軍に脆くも敗れたところを見ても、この臆斷は誤りないと思はれる。
全國の大半以上を占める幕府の淘軍力を以てしても、征長戰では、高杉晋作の奇襲戰に敗北した幕軍ではなかつたか。しかも戊辰の役一週間前に、幕府の親藩中の最親幕派の紀州藩、譜代大名中の最雄藩彦根藩までが、親朝的態度に轉向しかけて居るではないか。どこに勝味があるといふのか。時代はすでに移つて居るのである。ここが見えるからこそ勝は、最後の幕府全體會議の席上で、敗れる氣で戰かうかと提言したのであらう。ところで、小栗の場合は、これは東海道遮斷の戰略では、完全に勝つと思つて居たらしいことは、幕府會議席上の語氣によつて察せられる。勝敗の見通しにおいても勝の方がすぐれて居たと思はれる。
こゝで、臣節問題に觸れて見る。小栗は、おのれの議容れられずと見るや、其采邑上州權田村に退いてしまつた。これも一つの態度であらう。同樣に主君の依託を受けて、江戸の混亂を緩和し暴發せんとする幕臣を抑へて、徳川家の運命を好轉するためのあらゆる手段をつくして、曲りなりにも七十萬石の封土を保たせることに成功し、江戸及江戸城を破壊から免れしめえたのも、立派な一つの態度であらう。
日本人の好みからいへば、小栗型が喝采されるであらうし、勝型は軽蔑されがちである。しかし、これは日本人の美點といはんよりは、むしろ缺點であらう。大國民としては、勝型に學ぶところが多いのである。そして、小栗が苦い滓を心に湛へて隠遁して居る間に、勝の行動には幾多の困難がまとひつき、死に直面したことさへしばしばあつたことは、勝の傳記によつて知る通りである。徳川慶喜は、小栗に感謝する以上に勝に對して感謝すべきであり、臣節問題においても、二人の比較は、この慶喜の感謝の度合に比例するものとと考へられる。
四
小栗の死は無殘である。あれまでにせずともと思はれるが、小栗にも不用意の點がないとはいへない。彼が江戸を去るの前夜、振武隊長澁澤成一郎に向かつて語つてゐる。
「予固より見る所ありて、當初開戰を唱へたけれども、行はれなかつた。今や主君恭順し、江戸は他人の有に歸せんとする。人心挫折し機は既に去つた。最早戰ふことは出來ない。假令會津桑名諸藩が東北諸侯を連衡し、官軍に抗した所で、將軍既に恭順せられたる以上は何の名義も立たないのである。況んや烏合の衆をや。數月の後には事應に定まるであらう。我等は主君を奉じで天下に檄すべし。三百年の徳澤施して人に在り。國家の再造難事ではないだろう。我等は時機の到來を待つの外なし。予はこれより去りて知行所權田に土着し、民を懐け農兵を養ひ、事あらば雄飛すべく、事なければ頑民となりて終るべし」
若しこの心構へにして眞なりとすれば、官軍にとつて明治新政府にとつて、一個の敵國たることは明らかであり、かうした氣持で居る以上、その動作にも心の片鱗が現れて、官軍の疑惑を受けることは、むしろ當然であらう。況んや、過去の小栗の歴史は、そのいづれをとるにしても、薩長的な官軍から自眼をもつて見られる事實が多すぎる程あるのである。警戒されるのも無理からぬであらう。この際の小栗としては、恭謙己れを持することが、明哲保身の道であつたと考へられる。
しかるに、一團の暴徒がこの權田村を襲つた際、小栗は手強くこれを撃退して、その武威を示したのである。時機の到來を待つだけの準備のある小栗である以上、その撃退ぶりも鮮かであつたらう。そこに、官軍の疑惑を生じ、小栗の平生を知つて居るだけに、今にして刈らずんばの心を起さしめたのであらう。禍機は崩したのである。
しかし、小栗としては、死はむしろ當然の運命ではなかつたらうか。勘定奉行、陸軍奉行として幕府の組織に参與して以來、幕府第一主義の立場から常に硬論を稱へ、征長再征の推進力となつて、將軍征長劇を仕立てあげたのは、小栗であり、其後も常にこの態度を變へなかつた。その點では、會津以上と見られるであらう。今や時いたつて、その敵黨の天下となつたのだとしたら、幕閣第一の硬論者としての小栗は死への覺悟も出來て居たらうし、その方が彼の氣象としても、むしろさばさばしたのではなからうか。
それにしても彼の死は痛ましい。會津、長岡なみに命は殘しておいてやるべきであつたらう。その識見において、勝と比較するからこそ劣つて居ようが、彼も又一方の雄である。その剛情我慢の性質と兼ねてこれを新日本に用ひたならば、益するところ少しとしないであらう。
小栗の死と、勝の大臣就任に對して、いさゝか遺憾を感ずるのは獨り筆者みではあるまい。
引用・参照
『明治維新運動人物考』田中惣五郎 著 昭和十六年六月二十八日發行 東洋書館
(国立国会図書館デジタルコレクション)
(一八七ー一九八頁)
九 勝安房と小栗上野 - 幕臣として - 2022.09.16
一
勝と小栗を對比して、その本質を論ずることがちかごろあちこちで行はれて居るやうである。昭和維新のかけ聲の賑かなこのごろ、この二人の行き方を再検討することは、決して無意義ではなからう。それ戰術として、節操問題として、時代の見通しの問題として、どの角度から見ても、興味あるテーマである。況んや、やゝもすれば、從来の維新史が薩長的立場からのみしばしば價値判斷を強制して居ると見られて居る以上、その點から考へても、この比較はとりあげられてよいやうに思はれる。
二
二人の思想の端的な現れは、その郡縣論において見られる。慶應二年、幕府が征長の軍を大阪まで進發させて、將軍親征の大がゝりな計畫を賞行したのであるが、財政つゞかず、士気振はず、加へて國際勢力の壓迫と、國内反對勢力の征長反對にあつて、幕閣はほとんど立往生の態であつた。その國内的反對勢力の先頭を承つて居たのが、大久保利通を中心とする薩藩であり、大久保は、公然と征長の道ならぬことを説いて、反對意見書を老中板倉勝靜に呈したであつた。この反對意見書は、いろいろと裏面工作によつて撤回せしめようとしたのであるが、成功せず、やむなく、薩軍の西郷らと善い勝海舟を起用せざるを得なくなつたのであつた。二年前の元治元年、八一八事變の改革派彈壓の餘威をかりて、その一黨と交通して居たと見られる神戸海軍操練所長の勝までを、一氣に壓迫して、江戸へ呼戻して蟄居を命じてしまつたのである。
この復活する勝に對して、小栗の説いたのが、有名な封建から郡縣への意見であつたのである。開國起源によると、
此時顯要官吏、平素余と快からざる者、余を見て愕然たらざるはなく、小栗上野其他兩三名、余を引いて別室到り竊かに議して日く、君今坂地より降命あり、必ず要路の議に與からん。知るが如く今危急の際也 。
政府佛蘭西に金幣幾許軍艦六隻を求む。到着次第一時に長を追討すべし。薩も亦其時宜に依りて是を討ぜむ、然して後、邦内に口を容るゝの大諸侯なし。更に其勢に乘じ悉く削小して郡縣の制を定めんとす。是れ尤も秘密の議既に大凡決定せり。君定めて同意を表するならむ。若し然らむには猶上坂して説く所あるべきなりと。
余今論じて時日を消するの益なく害あるを察して口を開かず。唯之を聞くのみ。後大坂に至つて板倉伊賀に閲す。且つ關東の審議如何を問はる。予謹んで答へ云ふ。郡縣の議は、萬國交際起るに當つて、當然の議なるべし。今我が徳川家、邦家萬世の爲めに諸侯を削小し、自ら政權を持して天下に號令せんとするは、大いに不可なるべし。眞に邦家の御爲めを以て此大事業を成さんと欲せば、先づ自ら倒れ、自ら削小して顧みず、賢を撰み能を擧げ.誠心誠意天下に愧づる事なき地位に立ち、然る後成すべきなり……」
この郡縣論の理解から見ると、小栗は、斷然勝の敵手ではない。郡縣制は、封建制の倒れた後にはじめて確立すもものであつて、「先づ自ら倒れよ」といふ勝の認識が正しいことはいふまでもなからう。しかるに小栗の理解する郡縣論といふのは薩長の如き反勢力を打倒したその上で、諸鍵を削小することをさすらしいのである。そして、薩がなくなり、長がなくなり、諸侯から削りとつた土地と人民をしからばどうしようとするのであらうか。前後の語勢から推して、それは當然徳川家に歸するものらしいが、だとすると、これは幕府を強化する以外の何ものでもなく、これをしも郡縣論とと考へたのだとしたら、その無理解に驚くのである。
もしまた全國を平定して後、徐ろに郡縣制を布くの意圖を藏したら、それは勝のとつた態度と五十歩百歩の相違でしかなく、徳川氏を自らの手で最も巧みに葬る以外方法はなかつたであらうと思はれる。しかし、反對勢力の蹶起なくして.或日突如として郡縣に變るなどゝいふことは、いさゝかでも歴史のあとを眺めた人の肯んじえないところであらう。
人は慶喜の大政奉還を以て、恭順の證とし、郡縣の第一歩と考へるかも知れぬが、形式的の大政奉還ならば、すでに慶應元年に行はれて居たのである。否、文久三年の將軍家茂の上洛が、その先驅とさへ見られるのである。すたはち、尊王攘夷の全國的氣運に押された幕府は、やむなく莫大の上洛費を乏しい財政の中から工面して、京都にいたつて、天子の御前において政を議したのである。形式的なものなら、この時すでに大政を奉還したともいへるのである。
しかも、幕府としては、反幕の氣勢がもり上つて、やがて倒幕に發展せんとする氣勢に脅え、かつは幕府の政權そのものを朝廷に歸し奉ることがかへつて政治運行の方法としては賢明なものであることを、慶應三年の兵庫開港問題の時知つたはずである。すなはち、事府の單獨意見で開港したからこそ全國攘夷の怨みの的となつたのである。そのくせ、八百萬石の威力を有する徳川の實力は、議論の際は斷然他を壓しうるのであるから、名を棄て實をとる方法としては、これに越したものはないのである。
筆者は決して慶喜がさうした意圖の下に大政を奉還したとは斷じたくないのである。事實、目先の見える弱い氣の型の、しかも將軍就任までは、朝廷と幕府の間に立つて緩衝地帶の立場に居た慶喜としては、かなり純粋の氣持で奉還したらうと思ふ。が、同時に、この易きにつく方法として形式的大政を易々として返上したであらうことも、返上前後の慶喜の動きと返上のし方から推察できるのである。否、その後の實質的返上にあたつて、猛然反噬して來たことによつて一層その意圖が明らかにされる。
つまり、徳川氏のもつ大政とは、八百萬石の土地と旗本八萬騎の武力から生まれたものであつて、その點では、薩摩とも、長州川とも。何らの差違はないはずである。だから、この力によつて得た大政を返上するといふことは納土までいつて、はじめて眞の大權返上となりうるのであらう。
徳川の臣下中眞に見透しの利く大量の人物かあつてこそ形式的大權と同時に、實質的の版籍をも奉還し、全國の藩の魁をなして、他藩の版籍までも止むなく返還せざるを得なくさせたら、これこそ素ばらしい頭惱の持主たりえたらうし、徳川のためにもなりえたであらうと思はれる。身を捨てゝた敵の薩長までもろともに同じ運命に立たしめるのである。
ところが、徳川のためを考へてこの擧に出た土佐藩の山内容堂も、その臣後藤象二郎も、はじめから徳川を主座として、天皇を擁した政治をのみ意圖して居たゝため、薩長の討幕によき口餌を與へてしまつたのである。勝の 「自ら掴れよ」といふ意味は、いづれとも推測しがたいが.これは後藤より一歩進んだものであらうことだけはたしかである。
ところが、小栗となると、徳川中心郡縣諭の持主であるだけに、薩長を動かして居る新時代的なものに對しては完全に盲目であり、たゞ薩長憎さと徳川第一主義の點から、猛烈に大政奉還と、これにつゞく辭官納土の要求に反發し、強硬に一戰主張したものである。もちろん、薩長が辭官納土をみずからせずして、徳川にのみ迫るのは、一應の非理であらう。しかし、三百年間政權の地位にあつた徳川としでは、完全に政權の地位から占め出されて居た薩長ののこの抗議に對しては一先づ聞くべき立場にあつたのである。しかも、明らかに朝廷の意志を體したりとする薩長に對して一戰以外策がないといふのは、あまりにも無策であらう。小栗は、盛んに戊辰の役の戰の無策を論じて居るが、小栗はそれ以上に大局的に無策であつたと攻撃されたら、何と答へるであらうか.斯かる無策の出兵をするといふことが、そもそも倒幕前夜の現象なのであり.小栗の無策も、その不可避的な現象と見れば見られぬこともなからう。第一に二倍に餘る會津桑名の兵が薩長の寡兵うち破られたといふことが、桐の一葉に秋を知る現象であり、よし小栗の巧緻な戰闘枝術を以てしても、新時代の武器と兵法に身を鎧つたいはゆる官軍に抗し得たかは疑問であらう。
勝が、小栗を評して、眼識局小にして、あまり學問の無かりし人といつて居り、これに異議をさしはさむ人もあるが、事實蘭學によつて鍛へられた勝の頭惱から見たら、小栗ならずとも、當時の幕閣首惱部のすべてがしかく見えたであらうととは、否みえないであらう。小栗も勝と同じ船で米國に渡り彼地浹を見て來たのであり、軍事にも産業にも一見識を持つていろいろの新施設を行つたことは事實であらうが、それとて識見や經驗のある下僚同僚等の力をかりぬとは斷定しえないのである。そこへ行くと、勝の方は、むしろ智慧を貸す方であつた、決して借りる側の人物ではない。
若し、二三の人だけで相談したりした揚合は、その郡縣論のごとく見當違ひの判斷をずるらしいのである。つまり、この郡縣論は、勝と小栗の思想と知識を知る上において、好箇の材料であると考へられる。
三
勝の臣節については、福澤諭吉の痩我慢説以來、あまり香ばしくないことになつて居る。これに反して、小栗は、むごい死に方こそしたものゝ徳川に殉じた一個の忠節の臣として賞せられて居るのであるが、こゝにも色々と問題はありうると思はれる。
臣節とは何ぞやといふことは、具體的な場合において、中々にむづかしい問題であらう。乃木將軍の殉死も、乃木將軍の歴史を知つてはじめて諒承と讃嘆の聲を發しうるのであつて、だれでもやつてよい行爲でないことは、けだし當然であらう。だから、徳川の爲に死ぬとか戰ふとかいふことだけが、臣節をつくすことだと考へたら、とんでもたい誤謬に陥るのである。
幕府か倒れるものであることは、達識の士はすでに知るところであり、慶喜將軍自身すらこれを知つて先づ大政奉還と稱する外濠を埋めたのである。此場合、あくまで大政奉還を拒んで、若し慶喜將軍がこれに從はざれ これを葬つて他の人を將軍に据えても、將軍の存在を維持繼續することが大義であるといふ場合は、慶喜を殺すことが忠義となりうることもないではなからう。しかし天下の大勢は、天朝にすべてを歸結せしむべきであるといふ傾向に滔々としてなりつゝあるのである。そして、曲りなりにもこれに慶喜が從はうとして居る際に、この勢いに抗して、この勢とあくまで一戰することを主張するものがありとしたら、その人は、時代に盲目であるか臣節を心得ぬ人として譏られるであらう。
なる程、薩長の人々は、あるひは官軍の名あつて實なきものも多かつたであらうが、人間の行爲は、官軍であるからといつて、截然と賊軍と異なる程の立派な個人になり變ることは出來るものではない。そこには不完全な人間の集合體があるだけであらう。しかし、彼等の爲さんとすることと、その目指す方向とが、官軍的でありとしたら、これは恕すべきものであらう。その個々の行爲を論じて責めることばかりして居つたら、すべては否定されざるを得ないことになる。
そして、當時の官軍の立場はしかるが如きものであり、これに對しても、慶喜は恭順を専一とすることを聲明して居るのである。だとしたらこの場合、慶喜の意志と、時勢の前に屈して、せめて徳川氏が有利な立場に立ち得るやうに取計らうべきが臣節ではなからうか。
徳川氏のために、潔く一戰を交へることは、快は快であらうが、これはむしろ相手の術中に陥つて、すべてを破滅せしめることであらう。征東軍の参謀長西郷は、出發前において徹底的討伐を大久保に申し送つて居る。これに對して一戰したとしたら徳川の宗廟は完全に破壊されることは論を俟たない。一戰して勝つと信ずるが如きは、慶喜の征長戰同樣認識不足も甚だしい。勝つものなら、伏見鳥羽の戰で勝つてゐるはずである。戰略はとにかくとして、辭官納地問題に憤慨しきつた幕兵の最強藩の會津を中堅とした大軍でありながら、二分の一、三分の一とさへいはれる官軍に脆くも敗れたところを見ても、この臆斷は誤りないと思はれる。
全國の大半以上を占める幕府の淘軍力を以てしても、征長戰では、高杉晋作の奇襲戰に敗北した幕軍ではなかつたか。しかも戊辰の役一週間前に、幕府の親藩中の最親幕派の紀州藩、譜代大名中の最雄藩彦根藩までが、親朝的態度に轉向しかけて居るではないか。どこに勝味があるといふのか。時代はすでに移つて居るのである。ここが見えるからこそ勝は、最後の幕府全體會議の席上で、敗れる氣で戰かうかと提言したのであらう。ところで、小栗の場合は、これは東海道遮斷の戰略では、完全に勝つと思つて居たらしいことは、幕府會議席上の語氣によつて察せられる。勝敗の見通しにおいても勝の方がすぐれて居たと思はれる。
こゝで、臣節問題に觸れて見る。小栗は、おのれの議容れられずと見るや、其采邑上州權田村に退いてしまつた。これも一つの態度であらう。同樣に主君の依託を受けて、江戸の混亂を緩和し暴發せんとする幕臣を抑へて、徳川家の運命を好轉するためのあらゆる手段をつくして、曲りなりにも七十萬石の封土を保たせることに成功し、江戸及江戸城を破壊から免れしめえたのも、立派な一つの態度であらう。
日本人の好みからいへば、小栗型が喝采されるであらうし、勝型は軽蔑されがちである。しかし、これは日本人の美點といはんよりは、むしろ缺點であらう。大國民としては、勝型に學ぶところが多いのである。そして、小栗が苦い滓を心に湛へて隠遁して居る間に、勝の行動には幾多の困難がまとひつき、死に直面したことさへしばしばあつたことは、勝の傳記によつて知る通りである。徳川慶喜は、小栗に感謝する以上に勝に對して感謝すべきであり、臣節問題においても、二人の比較は、この慶喜の感謝の度合に比例するものとと考へられる。
四
小栗の死は無殘である。あれまでにせずともと思はれるが、小栗にも不用意の點がないとはいへない。彼が江戸を去るの前夜、振武隊長澁澤成一郎に向かつて語つてゐる。
「予固より見る所ありて、當初開戰を唱へたけれども、行はれなかつた。今や主君恭順し、江戸は他人の有に歸せんとする。人心挫折し機は既に去つた。最早戰ふことは出來ない。假令會津桑名諸藩が東北諸侯を連衡し、官軍に抗した所で、將軍既に恭順せられたる以上は何の名義も立たないのである。況んや烏合の衆をや。數月の後には事應に定まるであらう。我等は主君を奉じで天下に檄すべし。三百年の徳澤施して人に在り。國家の再造難事ではないだろう。我等は時機の到來を待つの外なし。予はこれより去りて知行所權田に土着し、民を懐け農兵を養ひ、事あらば雄飛すべく、事なければ頑民となりて終るべし」
若しこの心構へにして眞なりとすれば、官軍にとつて明治新政府にとつて、一個の敵國たることは明らかであり、かうした氣持で居る以上、その動作にも心の片鱗が現れて、官軍の疑惑を受けることは、むしろ當然であらう。況んや、過去の小栗の歴史は、そのいづれをとるにしても、薩長的な官軍から自眼をもつて見られる事實が多すぎる程あるのである。警戒されるのも無理からぬであらう。この際の小栗としては、恭謙己れを持することが、明哲保身の道であつたと考へられる。
しかるに、一團の暴徒がこの權田村を襲つた際、小栗は手強くこれを撃退して、その武威を示したのである。時機の到來を待つだけの準備のある小栗である以上、その撃退ぶりも鮮かであつたらう。そこに、官軍の疑惑を生じ、小栗の平生を知つて居るだけに、今にして刈らずんばの心を起さしめたのであらう。禍機は崩したのである。
しかし、小栗としては、死はむしろ當然の運命ではなかつたらうか。勘定奉行、陸軍奉行として幕府の組織に参與して以來、幕府第一主義の立場から常に硬論を稱へ、征長再征の推進力となつて、將軍征長劇を仕立てあげたのは、小栗であり、其後も常にこの態度を變へなかつた。その點では、會津以上と見られるであらう。今や時いたつて、その敵黨の天下となつたのだとしたら、幕閣第一の硬論者としての小栗は死への覺悟も出來て居たらうし、その方が彼の氣象としても、むしろさばさばしたのではなからうか。
それにしても彼の死は痛ましい。會津、長岡なみに命は殘しておいてやるべきであつたらう。その識見において、勝と比較するからこそ劣つて居ようが、彼も又一方の雄である。その剛情我慢の性質と兼ねてこれを新日本に用ひたならば、益するところ少しとしないであらう。
小栗の死と、勝の大臣就任に對して、いさゝか遺憾を感ずるのは獨り筆者みではあるまい。
引用・参照
『明治維新運動人物考』田中惣五郎 著 昭和十六年六月二十八日發行 東洋書館
(国立国会図書館デジタルコレクション)