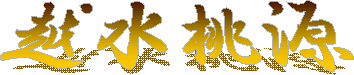大東亞戰爭の原因 ― 2023年02月06日 22:22
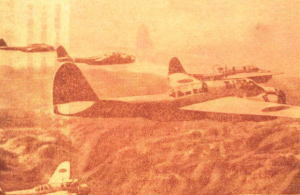
『史考大東亞戰爭』 陸軍中將 中井良太郎 著
(13-14頁)
第一章 緒 説 2023.02.06
皇紀二千六百一年、昭和十六年十二月八日、是れ程、偉大なる史實を後世に貽す暦日は、世界有史以来四千年を通じて又とあるまい。
筆者も生を皇國に享けて五十五年、身を軍籍に置いて約四十年、此の間、個人としては、感激と歡喜に滿ちた日も尠なしとしなかつたが、此の日程、國民的な感激と歡喜とを覺えた日は未だ曾て無かつた。十二月八日正午ラジオの前に直立して、宣戰の詔書を謹聽したときの心持ちは到底拙筆の能く盡す所ではない。
宣戰の詔書を拝誦し、政府の聲明、外交經過及び對米覺書を見、又首相及び外相の、議會其の他の機會に於ける演説を聽けば、大東亞戰爭に付、吾等の駄辯や拙文を弄する餘地も無いのであるが、宣戰の詔書を拝して、今後吾等國民は此の聖戰完遂の爲、如何に御奉公申すべきやを考へると、其處には全國民に共通する事項と、各々職域、身分地位に應じ奉公せねばならぬ特別の事項とがあるやうに思ふ。吾々公共團體等の依嘱を受け、微力乍ら、今日迄、銃後國民指導の一端に携はつて來た者としては、此の際更に、大東亞戰爭の原因、眞義、目的、理想、政治經濟上の眞價、作戰統帥等に付充分に考察し、皇國の必勝疑ひ無き所以と、此の戰爭の崇高偉大、古今に絶する理由とを明確に意識し引續き微力を銃後國民指導に捧ぐるを必要とする。そして此等諸事項を考察するの道は種々あらうと思ふが、筆者は史觀に立つて考察したいと思ふのが、此れを執筆する主眼である。本書に特に「史考」と銘誌したのは、之が爲である。茲に史考と稱するは、過去の戰爭史を見て、之を大東亞戰爭の現實と比較し、現實と過去の史實を見て此の戰爭將來を判斷しようと云ふ意である。
筆者は斯樣に考へ、職分奉公の一端として本册子を執筆したである。元より東西古今の戰爭史を取りて詳述することは、諸種事情が之を許さないで、米英の罪惡挑戰史を抉摘し、皇國及皇戰の崇高且偉大性及び其の正義が東西古今に絶し、皇國の必勝疑ひ無き所以を重點とし、史考に立ち、極めて常識且つ通俗平易に説述致して見たいと思ふのである。
(15-16頁)
第二章 大東亞戰爭の原因
謹で宣戰の詔書を拜讀し、戰爭原因を要約申上ぐれば、
東亞の安定を確保し以て世界の平和に寄與し給はんとすの明治大正兩大御世以來の宏遠且つ神聖なる皇謨に基き給ひ、列國との交誼を篤くし萬邦共榮の樂を 偕にし給はんとする皇國國交の要義に對し、米英が太平洋制覇卽世界制覇の非望野心を遂げんとし、經済上軍事上凡ゆる非道極悪の手段や策謀を以て皇國を 脅威し屈從せしめんことを企圖し、爲に皇國の宏遠神聖の皇謨も水泡に歸し、皇國の在立も正に危殆に瀕するに至つたので、皇國は自存自衛の爲蹶然起つて一切の障礙を破碎するの外策なきに至つた。
と云ふことに相成らうかと拜察する。
故に、米英の太平洋制覇卽世界制覇の非望野心こそ眞に今次戰爭を誘起 挑發した原因であり、皇國は其の權威と、皇國を初め大東亞諸民族の生存を確保し自衛を完うせんが爲、已むに已まれず武力に訴へたのである。之を個人に譬へたならば、強盜殺人犯行に對する正當防衛と同樣で、米英は正に強盗殺人鬼であり、皇國は之を取押へて警察署へ突き出さうとする劍聖的義人である。
米英の世界制覇の野心は既に遠き以前から傳統一貫して居る。依て筆者は章を改めて、此の非望を史的に解剖抉摘しよう。
(17-41頁)
第三章 大東亞戰爭を挑發した米國の野心と横暴非道
通 説
「太平洋を制する國は世界を制する」。之は地政學者の定論だが、地政學者ならずとも常識でも分ることである。況んや飽くなき慾望と野心とに充ちた米國の政治家や軍人や 猶太財閥をやである。此の米國の太平洋制覇卽世界制覇の野望非道こそ、大束亞戰爭を挑發した原動力なのだ。大東亞戰爭を叙述するには先づ米國の此の野望覇心と横暴非道とを解剖抉摘してかゝらねばならぬ。
(一) 米國の太平洋上の架橋的工作と其の惡辣手段
米國は是迄日本以外の太平洋面に對し、どんな手を打つたか、之れは周知 のことではあるが、順序として其の主たるものを列記すると、
太平洋東岸に於ては
(1) 米本國沿岸の海陸空軍の基地の建設
(2) アラスカ の領有と其の防備
(3) パナマ運河開鑿と其の獨占
太平洋中に於ては
(1) 布哇の併合及び眞珠灣海軍基地の建設防備及び其の西南方諸島の領有と軍事施段
(2) 比島占領とマニラ灣の海軍基地の建設防備
(3) グアム島の占領と其の防備
(4) 太平洋中の有線無線の通信施設、及び南北太平洋上の航空路の開拓と其の防備
(5) アリユーシアン群島の領有と其の海軍及空軍基地の設定
西太平洋沿岸に對しては
(1) 支那大陸に於ける各種經濟權益の割込獲得
(2) 蘭印方面に於ける必須國防資源の獲得等である。
以上の諸工作を大觀すると、全く「太平洋東岸から其の西岸迄の大橋梁架設と其の橋梁防備施設の設定」と云つた形である。
彼れは何故に斯樣なことをしたか、夫れは云はずもがな、「太平洋の制海、制空兩權を確保して支那大陸に進出し、自國製品の大市場を獲得し、一方自給自足し得ざる國防必須の資源(例へばゴム錫等)を入手して世界制覇を爲さむとするに在る」。之は彼れの太平洋政策の主眼である。
彼れ米國が、右諸工作の爲、どんな内訌を取っつたか、夫れは横車押しと惡辣と云ふ一語に盡きる。布哇王國の内訌に乘じて其の内政に干涉して之を併合し、西班牙の衰運に乘じて、故意にメエーン號事件を企み、米西戰爭を挑發誘起して比島を占領した如きは其の顯著なる例である。其の他、太平洋諸島の領有も一つとして横車押したらざるはない。
(二) 米國の對支政策
米國が 今日迄、強調し績けた支那に於ける機會均等、門戸解放、支那領土の保全等は、國際道徳からでもなければ國際正義からでもない。全く東洋進出に立ち遅れた割込み策であり、日本の大陸進出封鎖策であり、支那の歡心を買つて支那大陸に利權を漁らんとする目的であることは見え透いて居る。彼れの支那に對し打つた手は、全く後述する日露戰爭以前、日本に對し打つた手の燒直し的の手に外たらない。賣恩、懐柔、支那米化策等に依る利權漁りである。
(三) 米國の對日政策 (第一期)
以上は今日迄に於ける日本以外に對する、米國の太平洋政策史の概觀であるが、彼れは日本に對しては如何なる手を打つたか、此の事も敢て説明する迄もないことであるが、顧みれば恨み骨髄に徹することが大部分であり、之が卽ち大東亞戰爭の根本原因であるから、先づ其の概要を叙述せねばならぬ。
怨敵米國が初めて我が神州を脅迫したのは、嘉永六年のペルリ來航であることは云ふ迄もない。曾て我が國内に親米熱が昂まつた頃、ヘルリは、我が開國の恩人だなどと云ふ者があつたが、見當違ひも亦甚だしいと云はねばならぬ。ペルリの來航は、日本を占領して東洋雄飛 の立脚点とせんとするにあつたことは、既に公開せられたぺルリの復命書に依り明らかである。恩人どころか、強盜 の類である。
所でぺルリが來て見たも々、當時の 三隻の小鑑と其の兵員とでは、到底日本を占領し得べくもない。そこで、彼れは開國貿易を迫り、其の間に徐々に日本を物にしようとした のだ。然らば、ペルリ西航と云ふ米國民族意識は、どうして起つたのであらうか。元々米民族の主部は英國から來たことは周知の
であるが、彼等移民は、英本國の誅求に堪へずして遂に叛旗翻へして獨立し、次いで段々大を成し北米大陸を西漸して茲に大國を建設し、遂に太平洋沿岸に出たものだ。そこで彼等の慾望は更に太平洋を超えて亞細亞に進出しようと 云ふ野心を誘起した。之がペルリの渡洋である。
當時亞細亞に於ては、英佛蘭等 の諸國は、既に多く の植民地を獲得し、其 の魔手は漸く日本にも及ばんとしつゝある。米國が切角、東洋に進出したものゝ日本は之を占領し得べくもない。他に求むべき土地もない。そこで考へた政策は、東洋に對する割込策、亞細亞進出の立遅の埋合せ策である。
ペルリが日本に來て脅かして見たも のゝ到底占領し得べくもなく、開國を強要したが 則座に成功はせぬ。更めて來航日本開國に成功したが、さて、次は日本をどうするかと云ふ事は當然米國 の政治家には考へる所であつたことは云ふ迄もない。そして爾來日本對して打つた手は、賣恩、懐柔、日本米化卽ち日本精神文化の破壊、日本去勢策等であつた。そして其の政策を胸中に秘して渡來した のは、ハリスであり、彼は當時歐洲諸國、就中、英國が常に日本に對し高壓的に臨んで居るのに對し、如何にも日本に好意を容せるかのやうに見せかけた。當時 の日本要路はハリス卽ち米國を有り難く思つたのは是非はない。
斯様な政策は爾後日露戰爭終了迄續いた、當代の日本人の中には喜んだ人も多かつたであらう、否其の後永く日本に親米熱かあつたのも無理もないことではあるが 事實は上述したやうな魂膽に基く僞裝親善に外ならぬ。
試みに、彼れ米國が日本へ輸出し、日本が撮取した宗教、思想、教學、政治、經濟、其の他物心双面の文化の迹をみれば、何れも日本精神文化の破壊用具たらざるものはあるまい。米國渡來の文化に依り、我が日本の精神文化は如何に蝕ばまれたか、徐かに考へて見れば何人も肯定し得やう。
日本は列強の壓迫覇心に拘らず、着々と國内體制を整頓強化し、固有の金甌無缺の國體の上に愈々近代國家の體制を樹立し、遂に、 日清戰爭に依り清國を屈した。
日清戰爭は、支那の老衰を曝露し、日本の前途有爲を如實に示した。此の結果は歐洲列強の支那蠶食熱を昂めると共に、日本に對しては、二樣の策を採つた。其の一は日本を抑へ付けようとする露國一派の策でおり、其の二は、日本を利用せんとする英米の策である。英國が先づ條約改正に應じたのも夫れであり、其の後日英同盟を結んだのも之が 爲めであるが、米國亦依然 僞装親日策を變へなかつた。
露國の太平洋進出、滿韓侵略の野心は遂に、日本の存立を甚だしく脅威した。吾等の先人は敢然として蹶起した。そして遂に國運を賭して露國と戰つた。
日露戰爭は吾等の勝利に歸した。日露戰爭に於ては米國は、どんな態度を取つたのだつたか、當時米國に使ひせられた現金子樞府顧問の御話に依ると、當初は米國の人氣は、あまり日本びいきではなかつたが、鴨綠江の戰闘に於ける日本軍 の快勝の報が、米國に傳はると、米國人氣がー變して日本に好意を寄せるやうになつたと云ふことだ。 爾來、時の大統鎮ルーズヴェル卜が日露兩國媾和の斡旋迄は、日本に支援を與へた。併し夫れは主として戰費貸與であつた。勿論米國の人氣が日本びいきになつたことは、日本にとつては、確に強味ではあつた。かうなつたのも、偏へに、大御稜威であることは申す迄もないが、陸海軍の連戰連勝と金子伯初め當路 の方々の努力でもあつた。 ―—米國は鴨綠江戰までは日和見である。 ―—乍併、媾和談判頃から戰爭終了直後、 竝に其の後の米國の對日態度や對日政策と思ひ比べるならば、米國は誠意誠心日本を支援した のではないことが 讀める。矢張り彼れ一流の利害關係、傳統の太平洋政策や其の他の狀況を見比べての「情は人の爲ならず」的な打算からの支援に過ぎなかつたことは、はつきりと看取することが出來るのである。
(四) 米國對日政策(第二期)
元々米國の太平洋政策は、上述 の通りであるから、當時の世界的強國と見られた露國が滿韓を占領し、日本を打倒して、太平洋に出ることは米國に取りては一大脅威であり、太平洋政策遂行上の恐るべき障碍である。故に日本を支援利用して、露國を西伯利に逐ひ込むことは米國としては當然考へた所であらねばならぬ。所で日本は大勝利を博した。かうなると彼れ米国は更に考へねばならぬ破目となつたに相違ない。
夫れかあらぬか、ポーツマス媾和談判に處するルーズヴェルトの態度を見ると、怪げなる點がある。 即ち、戰勝 の榮冠は之れを日本に與へるが、戰勝に依る偉大なる物的利得は日本に與へまい。露國は戰敗者だが、世界的強國の體面を傷けず、爾後に於ける米國 の國交にも支障なからしめやうとした心意は ありありと讀める。要するに、露國は之を西伯利へ追返へせば宜しい、さりとて日本をして將來著しく大を成さしめてはならぬと云ふのが、ルーズヴェルト の考へであつたと判断せざる得ざるものがある。露國ウヰッテが、恰も戰勝國の 使節の如く振舞ひ、棒太の半分の割壌と滿鐵南半分の譲渡と沿海洲の漁業權を認むることを以て談判の梟りを付け、皇帝より其 の功を賞せられて伯爵を授けられた裏面には、ルーズヴェルトの指金があつたと當時傳へられたものである。假りに百步譲つて、夫は餘り穿ち過ぎた考察だとするも、戰爭直後から、手の裏を反す如く一變した米國 の對日態度と對日政策とを見れば、彼れ米國が、日露戰爭間、我が日本を支援した のは斷じて誠意から出たものでは ないことは一點の疑ひない所である。
日露戰爭に於て、彼れ米國が我が日本を支援した理由は、尚此のほかにも あることが考へられる。其の一つは、露国における 猶太民族の解放で、他の一つは、米國自身が満洲方面に進出の野心のあつたことである。
露國の帝政時代、在露猶太人が著しく迫害せられたことは史上著明な事實であるが、米國に於ける富豪と云はれる者 の大部分は猶太人で、所謂猶太財閥である。猶太財閥が底力となりフリーメーソンなる秘密結社を作り世界陰謀 の中心勢力となつて居ることは、はつきり認識し得る所であるが、此 の結社の企圖する所は、世界を猶太人の支配下に置かうとするに在る。日露戰爭に於て、日本對し財的援助を與へたのは主として在米猶太財閥で、彼等の眞意は日本を勝す のではなく、日本を勝たすことに依り、在猶太民族を解放せんとするに在つた。そして日本に對する戰費貸與は、 謂はゞ高利貸的な 氣特で、戰後日本の疲弊に乘じて、日本の戰果を横取りしやうと云ふ底意もあつたことは、戦爭末期に於ける露國の國内動亂に於ける猶太人の動き、戰後、露國内 の猶太人の解放や、戰爭直後ハリマンの滿鐵共同經營提議でもよく分ることである。
ハリマンの滿鐵共同經營提議とはどんな事であつたかと云ふに、丁度ポーッマス條約締結の直後、まだ、全權大使小村候が、病氣靜養 の爲渡米して居る頃であつた。時の米國鐵道王と云はれたハリマンと云ふ男が、日本の政府に 對し滿鐵をば日米兩國の出資で經營したいと申込んだ。日本は戰後財政が疲弊して居る のであるから、政府當局も元老諸公も、此のハリマンの提議に同意を興へ、之を米國で靜養中 の小村侯に打電した。小村侯は驚いた、こんな契約を結んだならば、 滿鐵は軈て米國の爲めに乘取られてしまふ。斯くては、日露戰爭に從軍した將兵や其の戰死者英靈に對して済まぬ のみならず、戰果を臺なしにしてしまう、之れは斷然契約を破棄せねばならぬと決心せられ、政府當局に意見具申せられた結果、ハリマンとの契約は破棄せられた、誠に危い所であつたが、小村侯の炯眼はよく危險から戰果を救ひ将た のであつた。
日露戰爭終了後は、米國の封日態度や封日政策は全く全くー變した。試みに年代を逐ふて之を概説しよう。
明治三十九年頃から米國加州方面の排日熱が著しく高まつた、そして日本學童の排斥と云ふ教學上 の差別待遇を始めた。元々排日の原因には色々あつたと傳へられて居るが、日本人恐るべしと云ふ疑心暗鬼もあつたであらうし、日本人を抑へ付けねばならぬと云ふ政策觀もあつたであらう、日露戰爭後日本が、米國の頤使に甘んぜないと云ふ腹癒せもあつたであらう。兎に角、彼れ米人 の本性を現はして來た。
明治四十二年になると、米國政府は突如として在滿日露鐵道の中立提議を出した。併し日本も露國も斯かる傍若無人の非禮提議を一蹴した。そして、之に依り却て日露の間が接近すると云ふ皮肉な結果を來たし、米國は頗ぶる男を下げた、けれども、彼れ米國としては、爾後の呍ひ懸りを作り又、 對内外的 に排日熱を作らんとする底意もあつたと思ふ。殊に支那に對し歡心を得ようとすることをも心にあつたとも考へられる。
明治時代の末期には、彼れ米國鐵道敷設や銀行業に關し滿洲に割込みを策すると共に、引續き本國に於ける排日熱を昂めつゝ一方依然として、日本内部に對する日本精神文化破壊策の手を益々強めて來た。
大正三年から歐洲戰爭が始まつた。日本は日英同盟の誼に依り、聯合國側に參戰し、獨逸の租借地青島を攻略し、西太平洋、印度洋は勿諭、地中海に迄も我が海軍が出動して、英國 の制海權確保に絶大なる援助を與へた。一方歐洲戰亂の爲、日本の貿易は飛躍的な好況を示し、産業も發達し、財政も豐かになつた。此の事は米國に取りては脅威を感じたであらう。日露戰爭に於て露國を撃破して一躍ー等國の列には入つたが、物的國力としては、まだまだ貧弱であつた日本が、歐洲戰爭に依り、物的國力も飛躍的に增進した のであるから、米國としては、之れは油斷はならぬ、日露戰争に於て強霧は之を西伯利へ再び逐込んだも のゝ、之に代つて日本が東洋に雄飛し出せば、彼れ米國の太平洋政策遂行に一大障害となるものと獨り合點し、又々日本へ對し一つの手を打つた。夫れは大正六年夏の西伯利出兵 の勧誘である。
日本は西伯利出兵に同意して、西伯利に於ける聯合軍の中堅となつたが、さて、出兵して見ると、米國は事每に日本に制肘を加へる、そして日本をして思ふやうに西伯利で活躍させない、其の内に彼れ米國は西伯利から撤兵して凉しい顔をして居る。當時既に帝政露國は亡びて過激派の天下となり、日本軍は西伯利の寒地に戰つて居る。一方、大正七年十一月、歐洲に於ては獨逸は遂に屈して休戰となり、次で、大正八年の巴里に於ける媾和會議となつた。此の頃より、世界に反戰軍縮熱が昂まつた、更にヂモクラシー思想は世界を風摩しめ始た、其の策源地は云ふ迄もなく米國であり、其の音頭取りは米大統領ウィルソンと其の一派であつた。悲しくも、日本は此 の惡風の風靡する所となり、加ふるに、當時、所謂、成金共の跋恩跋扈となり、思想混亂、國風は頽れ、精神的に見れぱ誠に危險なる狀況であつた。日本の思想界や精神界を、斯く混亂に導いた原動力は米國であり、心なき日本の指導者や同胞は、此の米國の魔手に踊つたものであることは否定出來ない事實であると今日多くの識者は考へて居ると思ふ。斯くして日本は約四年の西伯利出兵も、獲る所、空しく、西伯利から撤兵したのであつた。西伯利出兵は筆者等の青年士官頃の事で あるが、當時の米國の態度や、我が國内の情勢を囘顧すれば今尚悲憤新たなるものがある。
思へば米國の西伯利出兵の勧誘は、全く、彼れが我が日本の世界大戰間増加した國力を消耗、蕩盡せしむると共に、日露の國交を悪化し、將來日露抗爭を績けしめんとする策であつたとしか思はれない。
大正八年巴里媾和會議に於ける米國の對日態度は、どうであつたか、夫れは全く日本に多くを與へず、支那全權を支援して其の恩を賣り歡心を求め、日本を壓迫して日本が世界大戰間支那に於て得たる權益を悉く吐き出させやうとするに在つた、そして夫れに成功し、剰さへ、支那を增長せしめ、爾後に於ける排日、侮日、抗日の素地を作つてしまつた。唯、彼れが日本の委任統治となした南洋群島、これこそ天が正義日本に與へた寶劍で、今日、彼れ米國は此の 寶劍で、悩まされて居るのも天誅でおると云ひ得やう。――南洋群島の太平洋に於ける戰略價値は金儲本位の米國には分らなかつたのだらう。――
巴里の媾和會議に於て、あれだけ日本を壓迫し乍ら、 尚慊らず、引き績き日本内部に 對しては誤れる平和熱を流布し、デモクラシー思想を喧傳し、軍縮熱を煽り、日本の精神文化破壊に主力を傾注した。日本 の朝野の識者は唯彼 れに追随するのみで、大衆は恰も噴火山上に踊るが如き光景を呈した。考ふれば誠に淺間しい極みであつた。事茲にに至つたのも、一に米國の魔手で あつたと斷言して憚らぬ。
日本に於ける軍縮熟、デモクラシー熱、誤れる平和熱の高まるを看て取つた米國は、頃宜しと大正十一年を以て華府會議を提唱し、列強之に同意した。
(五) 米國の對日政策(第三期)
日露戰爭後からの手を代へ品を代へて日本に壓迫を加へた米國が、其の味を占めて更に日本壓迫の手を強化した。
華府會議に於ては、彼れは米國第一主義に自惚れ、此 の會議をリードした。英佛伊も、戰勝國とは云ひ乍ら、戰爭の創痍は深大であり、日本亦上述のやうであるから、彼れ米國が一切我儘を爲し、世界を我物顔に振舞つたことは云ふ迄もない。彼れは日本を如何に壓迫したか、今日迄吾等の恨み骨髄に徹する所で周知のことではあるが、茲に簡單に述べて置かう。
華府會議に於て日本に與へた壓迫と侮辱は、 (1)五・五・三の海軍主力艦比率の無理押付け、(2)理不盡極まる太平洋防備制限、(3)日本の在支權益の無理やり吐出し、(4)日英同盟の強制的破棄、(5)九ケ國條約の締結、 (6)四國條約の締結等で ある。
海軍主力艦比率と太平洋防備の制限は全く無理不當、理不盡極まるもので殊に其の折衝間、我が第一の精鋭陸奥を未成鑑なりと、まるで駄々ツ子の云ふが如き暴論を吐き、其の既成艦たるを認識せざる得なくなると、自分の方では、新たに之に對抗する二艦を造つて五の比率としたと云ふが如き摸暴を敢てした、此の横暴に依り造つた鬼子的な一艦は、比の開戰當初、布哇で轟沈せられたウェスト、バージニヤで ある。何と云ふ皮肉であらう。天誅とは正に此の事だ、夫れは兎に角として、主力艦比率を日本に優越せしめ、理不盡極まる太平洋防備制限を押し付けたのは、 言はずもがな、彼れ米國が太平洋の制海權を獲得せんとする爲である。
日本の在支權益を無理やりに吐き出させ、九ケ國條約を結んだのは、要するに日本の大 陸進出封じ策であり、彼れの支那割込み策の完成の積りであつた。
日英同盟の強制破棄は、東洋に於ける日本孤立策であることは云ふ迄もない。勿論、吾等は老獪なる英國、利己主義の本尊のやうな英國と何時迄も手を握ることを欲した者ではない。英國などと同盟することは、孤の化けた美人と結婚同棲するやうなものであるから、日英同盟破棄其のものには痛痒も感ぜず、些の愛著もないが、米國が日本を孤立に陷れやうとする奸策には慊なかつた。
四國條約は當時日英同盟に代はる太平洋の平和雜持策と云はれた。併し之は逆に開戰前の對日包囲陣に轉換して居る。然も當時此の條約は、日本に對する太平洋義務の加重を目的とするものだと論ぜられた人もある、尤もな次第であると云へよう。
大正十二年日本は大震災に襲はれ帝都は、全く燒野原と化した。華府會議に於て壓迫せられた日本は、其の翌年更に此の大天災に見舞はれたのであるから、手も足も出なからうと見て取つた米國は、遂に、日本人を完全に米國及其屬領から排斥してしまつた。夫れは大正十三年で、日本人移民は絶對に入國を禁止せられ、土地の所有も禁止されてしまつた。侮日も亦甚だしいと謂ふべしだが、日本は遂に泣寢入となつてしまつたのであつた。
明治の末期頃から萠した米國の排日は茲に完成したのみならず、之れと前後して、英國も其の殖民地を閉鎖して日本人を入れしめず、他の列強皆之に倣ふやうになつた。彼れ米國はかうして、益々日本を島國内に監禁する策を執つたのである。
昭和二年になると彼れ米國は、不戰條約を提議した。實は平和の美名に匿れた我儘者米國が、被壓迫國の奮起に對し、戰爭誘發の責任を負はしめんとする魂膽であつた。思ふに、巴里媾和會議以來十餘年、日本を壓迫し抜いたが、尚飽き足らず、今後も更に日本を壓迫しよう。併し、若しかすると日本が奮起するかも知れない。此の場合には不戰條約に名を藉りて日本を戰爭挑發者にしてしまうと云ふ見え透いた魂膽なのだ。併し日本は條件を附しての批准であつたから其の災厄からは免れた。
華府會議以來、我が海軍は五・五・三の比率を補ふべく必死の努力を續けた。其の第一は補助艦艇の充實と航空部隊の整備擴充、第二は將兵の猛訓練即ち精神的及技術的訓練の優越、第三には、一艦の力の増強で、之は其の比率を補ふ重點であつたと聞いて居る。之れが實を結んで今日の偉大なる戰力及戰果となつた云ふ見方をする人が多い。禍福は、あざなへる繩の如しとは云ひ乍ら、二十餘年の我が海軍の苦心と努力に對しては今更乍ら衷心から敬意と謝意とを拂うはずには居られない。
華府會議に於て主力艦比率や太平洋防備制限を行つたものゝな、我が海軍は他の戰カを、ぐんぐん伸ばして行く、大震災後の復興も案外早く日本國力も立直りを見せた。日本壓迫に寧歳なき怨敵米國としては又しも、日本壓迫の新手を考へた。
夫れは昭和五年のロンドン會議である。此の會議は結局補助艦比率制限で、吾等は遂に總決算的に海軍力を拘束せられ、悲憤禁ぜなかつた。五・一五事件も實に此の悲憤の爆發であつたことは記憶尚新たである。
巴里媾和會議から、ロンドン會議迄打續く外交的日本壓迫と併行して、彼れ米國は我が日本内部の破壊、攪亂の手を更に強めた。此の魔手の爲、日本内部は如何ばかり、禍を受けたかは、第一次世界大戰後から昭和の初頃迄の國内情勢を囘顧すれば明らかであらう。
一方支那に對しては、賣恩、懐柔、支那米化を目指して著々と工作を進め、支那に於ける利權を漁り抜くと共に英国と呼應して、排日の推進力となつた。そして次第に日本の勢力を支那大陸から 驅逐せんと唯是れ努めると云ふ有樣であつた。
記述は前後したが、千九百二十四年であつたと思ふ、米國は露骨にも國防方針を發表した。共の要旨は東洋に對しては支那の門戸解放、機會均等、領土保全の政策を基本とし、此の基本政策遂行の爲必要なる軍備を整へる、そして、東洋に對しては、必要あらば、進攻作戰を行ふのだと云ふのである。——今日彼の面は見ものである。——
日本を抑へ付けるだけ押へ、揚句の果ては東洋に進攻すると云ふのである。何と云ふ傲慢無禮の方針であるか、之が今日の體爲となつたのだが、正に之れ驕者不久の天警である 。
飜つて大正の末期頃からの支那を見れば、蔣一派の排日は年一年と昂じ、排日より侮日抗日へと推移し、遂に昭和六年九月十八日の柳條溝事件を惹起し、日本も景早、勘忍袋の緖も切れ、決然として正義の武力に訴へざるを得なくなつた。爾來滿洲事變となり、皇軍は 張學良の兵政兩權を打倒して滿洲建國を援け、滿洲の建國を見るに至つたが、滿洲事變間は、彼れ米國は國際聯盟の後據と爲り、国際聯盟を操つて、終始吾等を恫喝した。吾等は昭和八年を以て國際聯盟に三行半を叩きつけて離脱してしまつた。
滿洲事變を顧みれば、蔣介石は、英米の傀儡であり、張學良は蔣介石の手先きでもあれば又英米直接の傀儡でもあつた。學良の父、作霖頃でも、米國滿洲に於ける利權漁りに其の餘念がなかつたこともあつた。
乍併、邪は勝つべくもない。彼れ米國の如何なる恫喝も術策も、吾等はビクともする者ではない。滿洲事變を契機として、湃然として日本精神は蘇つた。昭和の四五年迄の、米國の魔手も漸次我が國内から拂拭せられ、デモクラシーも、日一日と其の影を消して行つた。筆者も滿洲事變勃發後既に對米英決戰の必要を諸所の講演に於て説いたが、十年前を囘顧して實に感慨無量である。――昭和十六年十一月初、筆者は講演の爲、水戸に赴き、丁度土浦在住の恩師たる某先輩に會つた。談偶々筆者が昭和六年暮、土浦に於ける講演の囘顧に及び、當時筆者が 對米英決戰論を主張したことを話會ひ時を移した次第であつた。――
日本は米國の壓迫に對し毅然として所信に向ひ邁進した。其の結果滿洲建國は
成り、滿洲國は年一年と立派な近代國家に育成せられて行つたが、蔣介石政權の排日侮日抗日は、年と共に募る計りである。一方北方蘇聯の軍備は益々な擴充せられ、其の思想宣傳は愈々巧妙化し、殊に支那大陸に於ける共産主義の浸潤は漸次深くなつて來た。我が日本は平和裡に日支共榮共存の原則に依り相提携し、共に防共に力を致さうとしたが、蔣の背後には英米ありて蔣を操つて居る。蔣亦英米を背後の力として之に依存して容易に我れに應じようともせぬ。
昭和の十一年には不幸にも、我が國内に、二・二六事件と云ふ一大不祥事が勃 發した。我が軍備は四圍の情勢より、擴充必須の狀況に在り、國内體制は此の不祥事刺激せられて革新せねばならぬと云ふ情況となつた。そして愈々、昭和十二年より軍備も擴充し、國内體制も潮次革新を企圖せられた。
是れより先、昭和七年上海事件起るや、皇軍の一撃に敗れた蔣は停戰を申出たが、爾來英米は主體となりて蔣をして益々軍備を充實せしむ べく極力支援を與へたことは匿れなき事實であつたが、昭和十二年頃になると蔣の軍備が大に増強せられた。
所で日本は昭和十二年度からの軍備充實である。だから英米としては、蔣をして日本と事を構えしむるは此の秋と思つたに相挺ない、蔣の態度は益々抗日的となつたのも其背後には英米の使嗾と尻押しがあつた爲めに外ならぬ。是れが昂じて遂に昭和十二年七月七日の盧溝橋事件の勃発となり、支那事變の發端となつた。
思へば、支那事變も蔣の無理解と私慾とからであるが、其の源を質せば、英米の後押しから起つたものであることは明確な事實である。支那事變を解決せんが爲めには、 所詮蔣の背後の英米を除かねばならぬことは、心ある者の常識で、恰も神功暴皇后が熊襲の叛は背後に新羅があるからである。宜しく新羅を撃てとの神誥で御征韓を御斷行遊ばされたと同樣の狀況であることは、識者の等しく考へた所であつたと思ふ。だが、我が日本では日支間の事は日支のみの間で解決することは、戰爭の禍を局限し、東洋平和否世界平和の爲めであると考へ、滿四年の間は、傀儡蔣を擊ち、背後の傀儡師米英を撃たうとしなかったのであつた。
一方、支那事變勃発以來の米英の態度は如何、今更歴史として叙述する迄もないが、一言にして盡せば、日本恫喝、日本軍作戰の妨害、莫大なる武器と財力とを以てする援蔣、拉に精神的援蔣であり、其事例は枚擧するに遑はない。併し我が方は忍べるだけは、忍んだ。
越えて昭和十四年頃になると、歐洲の天地の風雲は漸く急を告げ、其の年遂に 歐洲戰爭となつた。英國は佛國と共に起ち、他の 弱少國亦英佛に從つたが、ソ聯は未だ起たざるのみならず、既に獨逸と不可侵條約を結び、英佛は他の弱少國と共に、精強獨逸に當らねばならなくなり、援将の事や、束洋のことは米國に依存するを要する破目となつた。米國は時到れりと、愈々露骨に援蔣を策し、日本彈壓の手を更に強めるやうになつた。併し吾等は、米國の恫喝など恐るるものではない。又別に好んで平和を害しようとするものでもない。非禮極まる彼の恫喝脅迫外交に對しても事理を盡して其の反省を求めたが、彼れは附上る計りであつた。
引用・参照・底本
『史考大東亞戰爭』 陸軍中將 中井良太郎 著 昭和十七年一月二十九日發行 二見書房
(国立国会図書館デジタルコレクション)
(13-14頁)
第一章 緒 説 2023.02.06
皇紀二千六百一年、昭和十六年十二月八日、是れ程、偉大なる史實を後世に貽す暦日は、世界有史以来四千年を通じて又とあるまい。
筆者も生を皇國に享けて五十五年、身を軍籍に置いて約四十年、此の間、個人としては、感激と歡喜に滿ちた日も尠なしとしなかつたが、此の日程、國民的な感激と歡喜とを覺えた日は未だ曾て無かつた。十二月八日正午ラジオの前に直立して、宣戰の詔書を謹聽したときの心持ちは到底拙筆の能く盡す所ではない。
宣戰の詔書を拝誦し、政府の聲明、外交經過及び對米覺書を見、又首相及び外相の、議會其の他の機會に於ける演説を聽けば、大東亞戰爭に付、吾等の駄辯や拙文を弄する餘地も無いのであるが、宣戰の詔書を拝して、今後吾等國民は此の聖戰完遂の爲、如何に御奉公申すべきやを考へると、其處には全國民に共通する事項と、各々職域、身分地位に應じ奉公せねばならぬ特別の事項とがあるやうに思ふ。吾々公共團體等の依嘱を受け、微力乍ら、今日迄、銃後國民指導の一端に携はつて來た者としては、此の際更に、大東亞戰爭の原因、眞義、目的、理想、政治經濟上の眞價、作戰統帥等に付充分に考察し、皇國の必勝疑ひ無き所以と、此の戰爭の崇高偉大、古今に絶する理由とを明確に意識し引續き微力を銃後國民指導に捧ぐるを必要とする。そして此等諸事項を考察するの道は種々あらうと思ふが、筆者は史觀に立つて考察したいと思ふのが、此れを執筆する主眼である。本書に特に「史考」と銘誌したのは、之が爲である。茲に史考と稱するは、過去の戰爭史を見て、之を大東亞戰爭の現實と比較し、現實と過去の史實を見て此の戰爭將來を判斷しようと云ふ意である。
筆者は斯樣に考へ、職分奉公の一端として本册子を執筆したである。元より東西古今の戰爭史を取りて詳述することは、諸種事情が之を許さないで、米英の罪惡挑戰史を抉摘し、皇國及皇戰の崇高且偉大性及び其の正義が東西古今に絶し、皇國の必勝疑ひ無き所以を重點とし、史考に立ち、極めて常識且つ通俗平易に説述致して見たいと思ふのである。
(15-16頁)
第二章 大東亞戰爭の原因
謹で宣戰の詔書を拜讀し、戰爭原因を要約申上ぐれば、
東亞の安定を確保し以て世界の平和に寄與し給はんとすの明治大正兩大御世以來の宏遠且つ神聖なる皇謨に基き給ひ、列國との交誼を篤くし萬邦共榮の樂を 偕にし給はんとする皇國國交の要義に對し、米英が太平洋制覇卽世界制覇の非望野心を遂げんとし、經済上軍事上凡ゆる非道極悪の手段や策謀を以て皇國を 脅威し屈從せしめんことを企圖し、爲に皇國の宏遠神聖の皇謨も水泡に歸し、皇國の在立も正に危殆に瀕するに至つたので、皇國は自存自衛の爲蹶然起つて一切の障礙を破碎するの外策なきに至つた。
と云ふことに相成らうかと拜察する。
故に、米英の太平洋制覇卽世界制覇の非望野心こそ眞に今次戰爭を誘起 挑發した原因であり、皇國は其の權威と、皇國を初め大東亞諸民族の生存を確保し自衛を完うせんが爲、已むに已まれず武力に訴へたのである。之を個人に譬へたならば、強盜殺人犯行に對する正當防衛と同樣で、米英は正に強盗殺人鬼であり、皇國は之を取押へて警察署へ突き出さうとする劍聖的義人である。
米英の世界制覇の野心は既に遠き以前から傳統一貫して居る。依て筆者は章を改めて、此の非望を史的に解剖抉摘しよう。
(17-41頁)
第三章 大東亞戰爭を挑發した米國の野心と横暴非道
通 説
「太平洋を制する國は世界を制する」。之は地政學者の定論だが、地政學者ならずとも常識でも分ることである。況んや飽くなき慾望と野心とに充ちた米國の政治家や軍人や 猶太財閥をやである。此の米國の太平洋制覇卽世界制覇の野望非道こそ、大束亞戰爭を挑發した原動力なのだ。大東亞戰爭を叙述するには先づ米國の此の野望覇心と横暴非道とを解剖抉摘してかゝらねばならぬ。
(一) 米國の太平洋上の架橋的工作と其の惡辣手段
米國は是迄日本以外の太平洋面に對し、どんな手を打つたか、之れは周知 のことではあるが、順序として其の主たるものを列記すると、
太平洋東岸に於ては
(1) 米本國沿岸の海陸空軍の基地の建設
(2) アラスカ の領有と其の防備
(3) パナマ運河開鑿と其の獨占
太平洋中に於ては
(1) 布哇の併合及び眞珠灣海軍基地の建設防備及び其の西南方諸島の領有と軍事施段
(2) 比島占領とマニラ灣の海軍基地の建設防備
(3) グアム島の占領と其の防備
(4) 太平洋中の有線無線の通信施設、及び南北太平洋上の航空路の開拓と其の防備
(5) アリユーシアン群島の領有と其の海軍及空軍基地の設定
西太平洋沿岸に對しては
(1) 支那大陸に於ける各種經濟權益の割込獲得
(2) 蘭印方面に於ける必須國防資源の獲得等である。
以上の諸工作を大觀すると、全く「太平洋東岸から其の西岸迄の大橋梁架設と其の橋梁防備施設の設定」と云つた形である。
彼れは何故に斯樣なことをしたか、夫れは云はずもがな、「太平洋の制海、制空兩權を確保して支那大陸に進出し、自國製品の大市場を獲得し、一方自給自足し得ざる國防必須の資源(例へばゴム錫等)を入手して世界制覇を爲さむとするに在る」。之は彼れの太平洋政策の主眼である。
彼れ米國が、右諸工作の爲、どんな内訌を取っつたか、夫れは横車押しと惡辣と云ふ一語に盡きる。布哇王國の内訌に乘じて其の内政に干涉して之を併合し、西班牙の衰運に乘じて、故意にメエーン號事件を企み、米西戰爭を挑發誘起して比島を占領した如きは其の顯著なる例である。其の他、太平洋諸島の領有も一つとして横車押したらざるはない。
(二) 米國の對支政策
米國が 今日迄、強調し績けた支那に於ける機會均等、門戸解放、支那領土の保全等は、國際道徳からでもなければ國際正義からでもない。全く東洋進出に立ち遅れた割込み策であり、日本の大陸進出封鎖策であり、支那の歡心を買つて支那大陸に利權を漁らんとする目的であることは見え透いて居る。彼れの支那に對し打つた手は、全く後述する日露戰爭以前、日本に對し打つた手の燒直し的の手に外たらない。賣恩、懐柔、支那米化策等に依る利權漁りである。
(三) 米國の對日政策 (第一期)
以上は今日迄に於ける日本以外に對する、米國の太平洋政策史の概觀であるが、彼れは日本に對しては如何なる手を打つたか、此の事も敢て説明する迄もないことであるが、顧みれば恨み骨髄に徹することが大部分であり、之が卽ち大東亞戰爭の根本原因であるから、先づ其の概要を叙述せねばならぬ。
怨敵米國が初めて我が神州を脅迫したのは、嘉永六年のペルリ來航であることは云ふ迄もない。曾て我が國内に親米熱が昂まつた頃、ヘルリは、我が開國の恩人だなどと云ふ者があつたが、見當違ひも亦甚だしいと云はねばならぬ。ペルリの來航は、日本を占領して東洋雄飛 の立脚点とせんとするにあつたことは、既に公開せられたぺルリの復命書に依り明らかである。恩人どころか、強盜 の類である。
所でぺルリが來て見たも々、當時の 三隻の小鑑と其の兵員とでは、到底日本を占領し得べくもない。そこで、彼れは開國貿易を迫り、其の間に徐々に日本を物にしようとした のだ。然らば、ペルリ西航と云ふ米國民族意識は、どうして起つたのであらうか。元々米民族の主部は英國から來たことは周知の
であるが、彼等移民は、英本國の誅求に堪へずして遂に叛旗翻へして獨立し、次いで段々大を成し北米大陸を西漸して茲に大國を建設し、遂に太平洋沿岸に出たものだ。そこで彼等の慾望は更に太平洋を超えて亞細亞に進出しようと 云ふ野心を誘起した。之がペルリの渡洋である。
當時亞細亞に於ては、英佛蘭等 の諸國は、既に多く の植民地を獲得し、其 の魔手は漸く日本にも及ばんとしつゝある。米國が切角、東洋に進出したものゝ日本は之を占領し得べくもない。他に求むべき土地もない。そこで考へた政策は、東洋に對する割込策、亞細亞進出の立遅の埋合せ策である。
ペルリが日本に來て脅かして見たも のゝ到底占領し得べくもなく、開國を強要したが 則座に成功はせぬ。更めて來航日本開國に成功したが、さて、次は日本をどうするかと云ふ事は當然米國 の政治家には考へる所であつたことは云ふ迄もない。そして爾來日本對して打つた手は、賣恩、懐柔、日本米化卽ち日本精神文化の破壊、日本去勢策等であつた。そして其の政策を胸中に秘して渡來した のは、ハリスであり、彼は當時歐洲諸國、就中、英國が常に日本に對し高壓的に臨んで居るのに對し、如何にも日本に好意を容せるかのやうに見せかけた。當時 の日本要路はハリス卽ち米國を有り難く思つたのは是非はない。
斯様な政策は爾後日露戰爭終了迄續いた、當代の日本人の中には喜んだ人も多かつたであらう、否其の後永く日本に親米熱かあつたのも無理もないことではあるが 事實は上述したやうな魂膽に基く僞裝親善に外ならぬ。
試みに、彼れ米國が日本へ輸出し、日本が撮取した宗教、思想、教學、政治、經濟、其の他物心双面の文化の迹をみれば、何れも日本精神文化の破壊用具たらざるものはあるまい。米國渡來の文化に依り、我が日本の精神文化は如何に蝕ばまれたか、徐かに考へて見れば何人も肯定し得やう。
日本は列強の壓迫覇心に拘らず、着々と國内體制を整頓強化し、固有の金甌無缺の國體の上に愈々近代國家の體制を樹立し、遂に、 日清戰爭に依り清國を屈した。
日清戰爭は、支那の老衰を曝露し、日本の前途有爲を如實に示した。此の結果は歐洲列強の支那蠶食熱を昂めると共に、日本に對しては、二樣の策を採つた。其の一は日本を抑へ付けようとする露國一派の策でおり、其の二は、日本を利用せんとする英米の策である。英國が先づ條約改正に應じたのも夫れであり、其の後日英同盟を結んだのも之が 爲めであるが、米國亦依然 僞装親日策を變へなかつた。
露國の太平洋進出、滿韓侵略の野心は遂に、日本の存立を甚だしく脅威した。吾等の先人は敢然として蹶起した。そして遂に國運を賭して露國と戰つた。
日露戰爭は吾等の勝利に歸した。日露戰爭に於ては米國は、どんな態度を取つたのだつたか、當時米國に使ひせられた現金子樞府顧問の御話に依ると、當初は米國の人氣は、あまり日本びいきではなかつたが、鴨綠江の戰闘に於ける日本軍 の快勝の報が、米國に傳はると、米國人氣がー變して日本に好意を寄せるやうになつたと云ふことだ。 爾來、時の大統鎮ルーズヴェル卜が日露兩國媾和の斡旋迄は、日本に支援を與へた。併し夫れは主として戰費貸與であつた。勿論米國の人氣が日本びいきになつたことは、日本にとつては、確に強味ではあつた。かうなつたのも、偏へに、大御稜威であることは申す迄もないが、陸海軍の連戰連勝と金子伯初め當路 の方々の努力でもあつた。 ―—米國は鴨綠江戰までは日和見である。 ―—乍併、媾和談判頃から戰爭終了直後、 竝に其の後の米國の對日態度や對日政策と思ひ比べるならば、米國は誠意誠心日本を支援した のではないことが 讀める。矢張り彼れ一流の利害關係、傳統の太平洋政策や其の他の狀況を見比べての「情は人の爲ならず」的な打算からの支援に過ぎなかつたことは、はつきりと看取することが出來るのである。
(四) 米國對日政策(第二期)
元々米國の太平洋政策は、上述 の通りであるから、當時の世界的強國と見られた露國が滿韓を占領し、日本を打倒して、太平洋に出ることは米國に取りては一大脅威であり、太平洋政策遂行上の恐るべき障碍である。故に日本を支援利用して、露國を西伯利に逐ひ込むことは米國としては當然考へた所であらねばならぬ。所で日本は大勝利を博した。かうなると彼れ米国は更に考へねばならぬ破目となつたに相違ない。
夫れかあらぬか、ポーツマス媾和談判に處するルーズヴェルトの態度を見ると、怪げなる點がある。 即ち、戰勝 の榮冠は之れを日本に與へるが、戰勝に依る偉大なる物的利得は日本に與へまい。露國は戰敗者だが、世界的強國の體面を傷けず、爾後に於ける米國 の國交にも支障なからしめやうとした心意は ありありと讀める。要するに、露國は之を西伯利へ追返へせば宜しい、さりとて日本をして將來著しく大を成さしめてはならぬと云ふのが、ルーズヴェルト の考へであつたと判断せざる得ざるものがある。露國ウヰッテが、恰も戰勝國の 使節の如く振舞ひ、棒太の半分の割壌と滿鐵南半分の譲渡と沿海洲の漁業權を認むることを以て談判の梟りを付け、皇帝より其 の功を賞せられて伯爵を授けられた裏面には、ルーズヴェルトの指金があつたと當時傳へられたものである。假りに百步譲つて、夫は餘り穿ち過ぎた考察だとするも、戰爭直後から、手の裏を反す如く一變した米國 の對日態度と對日政策とを見れば、彼れ米國が、日露戰爭間、我が日本を支援した のは斷じて誠意から出たものでは ないことは一點の疑ひない所である。
日露戰爭に於て、彼れ米國が我が日本を支援した理由は、尚此のほかにも あることが考へられる。其の一つは、露国における 猶太民族の解放で、他の一つは、米國自身が満洲方面に進出の野心のあつたことである。
露國の帝政時代、在露猶太人が著しく迫害せられたことは史上著明な事實であるが、米國に於ける富豪と云はれる者 の大部分は猶太人で、所謂猶太財閥である。猶太財閥が底力となりフリーメーソンなる秘密結社を作り世界陰謀 の中心勢力となつて居ることは、はつきり認識し得る所であるが、此 の結社の企圖する所は、世界を猶太人の支配下に置かうとするに在る。日露戰爭に於て、日本對し財的援助を與へたのは主として在米猶太財閥で、彼等の眞意は日本を勝す のではなく、日本を勝たすことに依り、在猶太民族を解放せんとするに在つた。そして日本に對する戰費貸與は、 謂はゞ高利貸的な 氣特で、戰後日本の疲弊に乘じて、日本の戰果を横取りしやうと云ふ底意もあつたことは、戦爭末期に於ける露國の國内動亂に於ける猶太人の動き、戰後、露國内 の猶太人の解放や、戰爭直後ハリマンの滿鐵共同經營提議でもよく分ることである。
ハリマンの滿鐵共同經營提議とはどんな事であつたかと云ふに、丁度ポーッマス條約締結の直後、まだ、全權大使小村候が、病氣靜養 の爲渡米して居る頃であつた。時の米國鐵道王と云はれたハリマンと云ふ男が、日本の政府に 對し滿鐵をば日米兩國の出資で經營したいと申込んだ。日本は戰後財政が疲弊して居る のであるから、政府當局も元老諸公も、此のハリマンの提議に同意を興へ、之を米國で靜養中 の小村侯に打電した。小村侯は驚いた、こんな契約を結んだならば、 滿鐵は軈て米國の爲めに乘取られてしまふ。斯くては、日露戰爭に從軍した將兵や其の戰死者英靈に對して済まぬ のみならず、戰果を臺なしにしてしまう、之れは斷然契約を破棄せねばならぬと決心せられ、政府當局に意見具申せられた結果、ハリマンとの契約は破棄せられた、誠に危い所であつたが、小村侯の炯眼はよく危險から戰果を救ひ将た のであつた。
日露戰爭終了後は、米國の封日態度や封日政策は全く全くー變した。試みに年代を逐ふて之を概説しよう。
明治三十九年頃から米國加州方面の排日熱が著しく高まつた、そして日本學童の排斥と云ふ教學上 の差別待遇を始めた。元々排日の原因には色々あつたと傳へられて居るが、日本人恐るべしと云ふ疑心暗鬼もあつたであらうし、日本人を抑へ付けねばならぬと云ふ政策觀もあつたであらう、日露戰爭後日本が、米國の頤使に甘んぜないと云ふ腹癒せもあつたであらう。兎に角、彼れ米人 の本性を現はして來た。
明治四十二年になると、米國政府は突如として在滿日露鐵道の中立提議を出した。併し日本も露國も斯かる傍若無人の非禮提議を一蹴した。そして、之に依り却て日露の間が接近すると云ふ皮肉な結果を來たし、米國は頗ぶる男を下げた、けれども、彼れ米國としては、爾後の呍ひ懸りを作り又、 對内外的 に排日熱を作らんとする底意もあつたと思ふ。殊に支那に對し歡心を得ようとすることをも心にあつたとも考へられる。
明治時代の末期には、彼れ米國鐵道敷設や銀行業に關し滿洲に割込みを策すると共に、引續き本國に於ける排日熱を昂めつゝ一方依然として、日本内部に對する日本精神文化破壊策の手を益々強めて來た。
大正三年から歐洲戰爭が始まつた。日本は日英同盟の誼に依り、聯合國側に參戰し、獨逸の租借地青島を攻略し、西太平洋、印度洋は勿諭、地中海に迄も我が海軍が出動して、英國 の制海權確保に絶大なる援助を與へた。一方歐洲戰亂の爲、日本の貿易は飛躍的な好況を示し、産業も發達し、財政も豐かになつた。此の事は米國に取りては脅威を感じたであらう。日露戰爭に於て露國を撃破して一躍ー等國の列には入つたが、物的國力としては、まだまだ貧弱であつた日本が、歐洲戰爭に依り、物的國力も飛躍的に增進した のであるから、米國としては、之れは油斷はならぬ、日露戰争に於て強霧は之を西伯利へ再び逐込んだも のゝ、之に代つて日本が東洋に雄飛し出せば、彼れ米國の太平洋政策遂行に一大障害となるものと獨り合點し、又々日本へ對し一つの手を打つた。夫れは大正六年夏の西伯利出兵 の勧誘である。
日本は西伯利出兵に同意して、西伯利に於ける聯合軍の中堅となつたが、さて、出兵して見ると、米國は事每に日本に制肘を加へる、そして日本をして思ふやうに西伯利で活躍させない、其の内に彼れ米國は西伯利から撤兵して凉しい顔をして居る。當時既に帝政露國は亡びて過激派の天下となり、日本軍は西伯利の寒地に戰つて居る。一方、大正七年十一月、歐洲に於ては獨逸は遂に屈して休戰となり、次で、大正八年の巴里に於ける媾和會議となつた。此の頃より、世界に反戰軍縮熱が昂まつた、更にヂモクラシー思想は世界を風摩しめ始た、其の策源地は云ふ迄もなく米國であり、其の音頭取りは米大統領ウィルソンと其の一派であつた。悲しくも、日本は此 の惡風の風靡する所となり、加ふるに、當時、所謂、成金共の跋恩跋扈となり、思想混亂、國風は頽れ、精神的に見れぱ誠に危險なる狀況であつた。日本の思想界や精神界を、斯く混亂に導いた原動力は米國であり、心なき日本の指導者や同胞は、此の米國の魔手に踊つたものであることは否定出來ない事實であると今日多くの識者は考へて居ると思ふ。斯くして日本は約四年の西伯利出兵も、獲る所、空しく、西伯利から撤兵したのであつた。西伯利出兵は筆者等の青年士官頃の事で あるが、當時の米國の態度や、我が國内の情勢を囘顧すれば今尚悲憤新たなるものがある。
思へば米國の西伯利出兵の勧誘は、全く、彼れが我が日本の世界大戰間増加した國力を消耗、蕩盡せしむると共に、日露の國交を悪化し、將來日露抗爭を績けしめんとする策であつたとしか思はれない。
大正八年巴里媾和會議に於ける米國の對日態度は、どうであつたか、夫れは全く日本に多くを與へず、支那全權を支援して其の恩を賣り歡心を求め、日本を壓迫して日本が世界大戰間支那に於て得たる權益を悉く吐き出させやうとするに在つた、そして夫れに成功し、剰さへ、支那を增長せしめ、爾後に於ける排日、侮日、抗日の素地を作つてしまつた。唯、彼れが日本の委任統治となした南洋群島、これこそ天が正義日本に與へた寶劍で、今日、彼れ米國は此の 寶劍で、悩まされて居るのも天誅でおると云ひ得やう。――南洋群島の太平洋に於ける戰略價値は金儲本位の米國には分らなかつたのだらう。――
巴里の媾和會議に於て、あれだけ日本を壓迫し乍ら、 尚慊らず、引き績き日本内部に 對しては誤れる平和熱を流布し、デモクラシー思想を喧傳し、軍縮熱を煽り、日本の精神文化破壊に主力を傾注した。日本 の朝野の識者は唯彼 れに追随するのみで、大衆は恰も噴火山上に踊るが如き光景を呈した。考ふれば誠に淺間しい極みであつた。事茲にに至つたのも、一に米國の魔手で あつたと斷言して憚らぬ。
日本に於ける軍縮熟、デモクラシー熱、誤れる平和熱の高まるを看て取つた米國は、頃宜しと大正十一年を以て華府會議を提唱し、列強之に同意した。
(五) 米國の對日政策(第三期)
日露戰爭後からの手を代へ品を代へて日本に壓迫を加へた米國が、其の味を占めて更に日本壓迫の手を強化した。
華府會議に於ては、彼れは米國第一主義に自惚れ、此 の會議をリードした。英佛伊も、戰勝國とは云ひ乍ら、戰爭の創痍は深大であり、日本亦上述のやうであるから、彼れ米國が一切我儘を爲し、世界を我物顔に振舞つたことは云ふ迄もない。彼れは日本を如何に壓迫したか、今日迄吾等の恨み骨髄に徹する所で周知のことではあるが、茲に簡單に述べて置かう。
華府會議に於て日本に與へた壓迫と侮辱は、 (1)五・五・三の海軍主力艦比率の無理押付け、(2)理不盡極まる太平洋防備制限、(3)日本の在支權益の無理やり吐出し、(4)日英同盟の強制的破棄、(5)九ケ國條約の締結、 (6)四國條約の締結等で ある。
海軍主力艦比率と太平洋防備の制限は全く無理不當、理不盡極まるもので殊に其の折衝間、我が第一の精鋭陸奥を未成鑑なりと、まるで駄々ツ子の云ふが如き暴論を吐き、其の既成艦たるを認識せざる得なくなると、自分の方では、新たに之に對抗する二艦を造つて五の比率としたと云ふが如き摸暴を敢てした、此の横暴に依り造つた鬼子的な一艦は、比の開戰當初、布哇で轟沈せられたウェスト、バージニヤで ある。何と云ふ皮肉であらう。天誅とは正に此の事だ、夫れは兎に角として、主力艦比率を日本に優越せしめ、理不盡極まる太平洋防備制限を押し付けたのは、 言はずもがな、彼れ米國が太平洋の制海權を獲得せんとする爲である。
日本の在支權益を無理やりに吐き出させ、九ケ國條約を結んだのは、要するに日本の大 陸進出封じ策であり、彼れの支那割込み策の完成の積りであつた。
日英同盟の強制破棄は、東洋に於ける日本孤立策であることは云ふ迄もない。勿論、吾等は老獪なる英國、利己主義の本尊のやうな英國と何時迄も手を握ることを欲した者ではない。英國などと同盟することは、孤の化けた美人と結婚同棲するやうなものであるから、日英同盟破棄其のものには痛痒も感ぜず、些の愛著もないが、米國が日本を孤立に陷れやうとする奸策には慊なかつた。
四國條約は當時日英同盟に代はる太平洋の平和雜持策と云はれた。併し之は逆に開戰前の對日包囲陣に轉換して居る。然も當時此の條約は、日本に對する太平洋義務の加重を目的とするものだと論ぜられた人もある、尤もな次第であると云へよう。
大正十二年日本は大震災に襲はれ帝都は、全く燒野原と化した。華府會議に於て壓迫せられた日本は、其の翌年更に此の大天災に見舞はれたのであるから、手も足も出なからうと見て取つた米國は、遂に、日本人を完全に米國及其屬領から排斥してしまつた。夫れは大正十三年で、日本人移民は絶對に入國を禁止せられ、土地の所有も禁止されてしまつた。侮日も亦甚だしいと謂ふべしだが、日本は遂に泣寢入となつてしまつたのであつた。
明治の末期頃から萠した米國の排日は茲に完成したのみならず、之れと前後して、英國も其の殖民地を閉鎖して日本人を入れしめず、他の列強皆之に倣ふやうになつた。彼れ米國はかうして、益々日本を島國内に監禁する策を執つたのである。
昭和二年になると彼れ米國は、不戰條約を提議した。實は平和の美名に匿れた我儘者米國が、被壓迫國の奮起に對し、戰爭誘發の責任を負はしめんとする魂膽であつた。思ふに、巴里媾和會議以來十餘年、日本を壓迫し抜いたが、尚飽き足らず、今後も更に日本を壓迫しよう。併し、若しかすると日本が奮起するかも知れない。此の場合には不戰條約に名を藉りて日本を戰爭挑發者にしてしまうと云ふ見え透いた魂膽なのだ。併し日本は條件を附しての批准であつたから其の災厄からは免れた。
華府會議以來、我が海軍は五・五・三の比率を補ふべく必死の努力を續けた。其の第一は補助艦艇の充實と航空部隊の整備擴充、第二は將兵の猛訓練即ち精神的及技術的訓練の優越、第三には、一艦の力の増強で、之は其の比率を補ふ重點であつたと聞いて居る。之れが實を結んで今日の偉大なる戰力及戰果となつた云ふ見方をする人が多い。禍福は、あざなへる繩の如しとは云ひ乍ら、二十餘年の我が海軍の苦心と努力に對しては今更乍ら衷心から敬意と謝意とを拂うはずには居られない。
華府會議に於て主力艦比率や太平洋防備制限を行つたものゝな、我が海軍は他の戰カを、ぐんぐん伸ばして行く、大震災後の復興も案外早く日本國力も立直りを見せた。日本壓迫に寧歳なき怨敵米國としては又しも、日本壓迫の新手を考へた。
夫れは昭和五年のロンドン會議である。此の會議は結局補助艦比率制限で、吾等は遂に總決算的に海軍力を拘束せられ、悲憤禁ぜなかつた。五・一五事件も實に此の悲憤の爆發であつたことは記憶尚新たである。
巴里媾和會議から、ロンドン會議迄打續く外交的日本壓迫と併行して、彼れ米國は我が日本内部の破壊、攪亂の手を更に強めた。此の魔手の爲、日本内部は如何ばかり、禍を受けたかは、第一次世界大戰後から昭和の初頃迄の國内情勢を囘顧すれば明らかであらう。
一方支那に對しては、賣恩、懐柔、支那米化を目指して著々と工作を進め、支那に於ける利權を漁り抜くと共に英国と呼應して、排日の推進力となつた。そして次第に日本の勢力を支那大陸から 驅逐せんと唯是れ努めると云ふ有樣であつた。
記述は前後したが、千九百二十四年であつたと思ふ、米國は露骨にも國防方針を發表した。共の要旨は東洋に對しては支那の門戸解放、機會均等、領土保全の政策を基本とし、此の基本政策遂行の爲必要なる軍備を整へる、そして、東洋に對しては、必要あらば、進攻作戰を行ふのだと云ふのである。——今日彼の面は見ものである。——
日本を抑へ付けるだけ押へ、揚句の果ては東洋に進攻すると云ふのである。何と云ふ傲慢無禮の方針であるか、之が今日の體爲となつたのだが、正に之れ驕者不久の天警である 。
飜つて大正の末期頃からの支那を見れば、蔣一派の排日は年一年と昂じ、排日より侮日抗日へと推移し、遂に昭和六年九月十八日の柳條溝事件を惹起し、日本も景早、勘忍袋の緖も切れ、決然として正義の武力に訴へざるを得なくなつた。爾來滿洲事變となり、皇軍は 張學良の兵政兩權を打倒して滿洲建國を援け、滿洲の建國を見るに至つたが、滿洲事變間は、彼れ米國は國際聯盟の後據と爲り、国際聯盟を操つて、終始吾等を恫喝した。吾等は昭和八年を以て國際聯盟に三行半を叩きつけて離脱してしまつた。
滿洲事變を顧みれば、蔣介石は、英米の傀儡であり、張學良は蔣介石の手先きでもあれば又英米直接の傀儡でもあつた。學良の父、作霖頃でも、米國滿洲に於ける利權漁りに其の餘念がなかつたこともあつた。
乍併、邪は勝つべくもない。彼れ米國の如何なる恫喝も術策も、吾等はビクともする者ではない。滿洲事變を契機として、湃然として日本精神は蘇つた。昭和の四五年迄の、米國の魔手も漸次我が國内から拂拭せられ、デモクラシーも、日一日と其の影を消して行つた。筆者も滿洲事變勃發後既に對米英決戰の必要を諸所の講演に於て説いたが、十年前を囘顧して實に感慨無量である。――昭和十六年十一月初、筆者は講演の爲、水戸に赴き、丁度土浦在住の恩師たる某先輩に會つた。談偶々筆者が昭和六年暮、土浦に於ける講演の囘顧に及び、當時筆者が 對米英決戰論を主張したことを話會ひ時を移した次第であつた。――
日本は米國の壓迫に對し毅然として所信に向ひ邁進した。其の結果滿洲建國は
成り、滿洲國は年一年と立派な近代國家に育成せられて行つたが、蔣介石政權の排日侮日抗日は、年と共に募る計りである。一方北方蘇聯の軍備は益々な擴充せられ、其の思想宣傳は愈々巧妙化し、殊に支那大陸に於ける共産主義の浸潤は漸次深くなつて來た。我が日本は平和裡に日支共榮共存の原則に依り相提携し、共に防共に力を致さうとしたが、蔣の背後には英米ありて蔣を操つて居る。蔣亦英米を背後の力として之に依存して容易に我れに應じようともせぬ。
昭和の十一年には不幸にも、我が國内に、二・二六事件と云ふ一大不祥事が勃 發した。我が軍備は四圍の情勢より、擴充必須の狀況に在り、國内體制は此の不祥事刺激せられて革新せねばならぬと云ふ情況となつた。そして愈々、昭和十二年より軍備も擴充し、國内體制も潮次革新を企圖せられた。
是れより先、昭和七年上海事件起るや、皇軍の一撃に敗れた蔣は停戰を申出たが、爾來英米は主體となりて蔣をして益々軍備を充實せしむ べく極力支援を與へたことは匿れなき事實であつたが、昭和十二年頃になると蔣の軍備が大に増強せられた。
所で日本は昭和十二年度からの軍備充實である。だから英米としては、蔣をして日本と事を構えしむるは此の秋と思つたに相挺ない、蔣の態度は益々抗日的となつたのも其背後には英米の使嗾と尻押しがあつた爲めに外ならぬ。是れが昂じて遂に昭和十二年七月七日の盧溝橋事件の勃発となり、支那事變の發端となつた。
思へば、支那事變も蔣の無理解と私慾とからであるが、其の源を質せば、英米の後押しから起つたものであることは明確な事實である。支那事變を解決せんが爲めには、 所詮蔣の背後の英米を除かねばならぬことは、心ある者の常識で、恰も神功暴皇后が熊襲の叛は背後に新羅があるからである。宜しく新羅を撃てとの神誥で御征韓を御斷行遊ばされたと同樣の狀況であることは、識者の等しく考へた所であつたと思ふ。だが、我が日本では日支間の事は日支のみの間で解決することは、戰爭の禍を局限し、東洋平和否世界平和の爲めであると考へ、滿四年の間は、傀儡蔣を擊ち、背後の傀儡師米英を撃たうとしなかったのであつた。
一方、支那事變勃発以來の米英の態度は如何、今更歴史として叙述する迄もないが、一言にして盡せば、日本恫喝、日本軍作戰の妨害、莫大なる武器と財力とを以てする援蔣、拉に精神的援蔣であり、其事例は枚擧するに遑はない。併し我が方は忍べるだけは、忍んだ。
越えて昭和十四年頃になると、歐洲の天地の風雲は漸く急を告げ、其の年遂に 歐洲戰爭となつた。英國は佛國と共に起ち、他の 弱少國亦英佛に從つたが、ソ聯は未だ起たざるのみならず、既に獨逸と不可侵條約を結び、英佛は他の弱少國と共に、精強獨逸に當らねばならなくなり、援将の事や、束洋のことは米國に依存するを要する破目となつた。米國は時到れりと、愈々露骨に援蔣を策し、日本彈壓の手を更に強めるやうになつた。併し吾等は、米國の恫喝など恐るるものではない。又別に好んで平和を害しようとするものでもない。非禮極まる彼の恫喝脅迫外交に對しても事理を盡して其の反省を求めたが、彼れは附上る計りであつた。
引用・参照・底本
『史考大東亞戰爭』 陸軍中將 中井良太郎 著 昭和十七年一月二十九日發行 二見書房
(国立国会図書館デジタルコレクション)