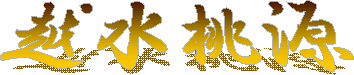高濱清 漱石氏と私 二 ― 2022年06月01日 09:07

『漱石氏と私』高濱清(高濱虚子)著
序
漱石氏と私との交遊は疎きがごとくして親しく、親しきが如くして疎きものありたり。その邊を十分に描けば面白かるべきも、本篇は氏の書簡を主なる材料として唯追憶の一端をしるしたるのみ。氏が文壇に出づるに至れる當時の事情は、略々此の書によりて想察し得可し。
大正七年正月七日
ほとゝぎす發行所にて
高濱虚子
永き日や欠伸うつして別れ行く === 漱石氏筆
漱石氏と私
(15-35頁)
二
明治二十九年の夏に子規居士が從軍中咯血をして神戸、須磨と轉々療養をした揚句松山に歸省したのはその年の秋であつた。その叔父君にあたる大原氏の家うちに泊つたのは一、二日のことで直ぐ二番町の横町にある漱石氏の寓居に引き移つた。これより前、漱石氏は一番町の裁判所裏の古道具屋を引き払つて、この二番町の横町に新らしい家を見出したのであつた。そこは上野という人の持家であつて、その頃四十位の一人の未亡人が若い娘さんと共に裏座敷を人に貸して素人下宿を営んでいるのであつた。裏座敷というのは六畳か八畳かの座敷が二階と下に一間ずつある位の家であつて漱石氏はその二間を一人で占領していたのであるが、子規居士が來ると決まつてから自分は二階の方に引き移り、下は子規居士に明け渡したのであつた。
私はその當時の實境を目撃したわけではないが、以前子規居士から聞いた話や、最近國へ歸つて極堂、霽月らの諸君から聞いた話やを綜合して見ると、大體その時の模樣の想像はつくのである。子規居士は須磨の保養院などにいた時と同じく蒲團は畳の上に敷き流しにしておいてくたびれるとその上に横はり、氣持がいゝと蒲団の上に起き上つたり、緣ばな位までは出たりなどして健康の回復を待ちつゝあつたのであらう。それから須磨の保養院に居る頃から筆を執りつゝあつた「俳人蕪村」の稿を纘ぎ、更に「俳諧大要」の稿を起すようになつたのであつた。子規居士が歸つたと聞いてから、折節歸省中であつた下村爲山君を中心として俳句の研究をしつゝあつた中村愛松あいしょう、野間叟柳、伴狸伴、大島梅屋の小學教員團體が早速居士の病床につめかけて俳句の話を聞くことになつた。居士は從軍の結果が一層健康を損じ、最早一圖に俳句にたずさはるよりほか、仕方がないとあきらめをつけ、さうでなくつても根柢から此短い詩の研究に深い注意を拂つてゐたのが、更に勇猛心を振ひ興して斯道に力を盡さうと考へていた矢先であつたので、それ等の教員團體、並びに舊友であるところの柳原極堂、村上霽月、御手洗不迷等の諸君を病床に引きつけて、殆んど休む間もなしに句作をしたり批評をしたりしたものらしい。その間漱石氏は主として二階にあつて、朝起きると洋服を着て學校に出かけ、歸つて來ると洋服を脱いで翌日の講義の下調べをして、二階から下りて來ることは少なかつたが、それでも時々は下りて來てそれらの俳人諸君の間に交つて一緒に句作することもあつた。子規居士はやはり他の諸君の句の上に○をつけるのと同じように漱石氏の句の上にも○をつけた。只他の人は「お前」とか「あし」とか松山言葉を使つて呼び合つてゐる中に、漱石氏と居士との間だけには君とか僕とかいふ言葉を用ひていた位の相違であつた。漱石氏は是等の松山言葉を聞くことや、足を投げ出したり頬杖をついたりして無作法な樣子をして句作に耽つている一座の樣子を流し目に見て餘いゝ心持もしなかつたらうが、その病友の病を忘れてゐるかの如き奮闘的な態度には敬意を払つてゐたに相違ない。殊に漱石氏は子規居士が親分らしい態度をして無造作に人々の句の上に○をつけたり批評を加へたりするのを、感服と驚きと可笑味とを混ぜたような眼つきをして見てゐたに相違ない。殊に又自分の句の上に無造作に○がついたり直が這入つたりするのを一層不思議さうな眼でながめていたに相違ない。
「子規といふ男は何でも自分が先生のような積りで居る男であつた。俳句を見せると直ぐそれを直したり圏點をつけたりする。それはいゝにしたところで僕が漢詩を作つて見せたところが、直ぐ又筆をとつてそれを直したり、圏点をつけたりして返した。それで今度は英文を綴つて見せたところが、奴さんこれだけは仕方がないものだから Very good と書いて返した。」と言つてその後よく人に話して笑つてゐた。
後年になつて漱石氏の鋭い方面はその鋒先をだんだんと嚢の外に表わし始めたが、その頃の――殊に若年であつた私の目に映じた――漱石氏は非常に温厚な紳士的態度の長者らしい風格の人のように思はれた。自然子規居士の親分氣質な動作に對しても別に反抗するような態度もなく、俳句の如きは愛松、極堂、霽月等の諸君に伍して子規居士の傘下に集まつた一人として別に意に介する所もなかつたのであらう。のみならず、この病友をいつくしみ憐れむような友情と、その親分然たる態度に七分の同感と三分の滑稽味を見出す興味とで、格別厭な心持もしないでその階下に湧き出した一箇の世界を眺めてゐたものであらう。そうして朝暮出入してゐる愛松、極堂らの諸君とは軌道を異にして、多くの時間は二階に閉籠つて學校の先生としての忠實なる準備と英文學者としての眞面目な修養とに力を注いでゐたのである。後年「坊つちやん」の一篇が出るやうになつてから、此松山中學時代の漱石氏の不平は俄かに明るみに取り出された傾きがあるが、當時の氏にはたとひそれらの不愉快な心持が内心にあつたとしても、それ等の不愉快には打勝ちつゝ、どこまでも眞面目に、學者として教師として進んで行く考であつたことは間違ひない。大學を中途で退學して新聞社に這入つて不治の病氣になつて居た子規居士と、眞直に大學を出て中學校の先生としていそしみつゝあつた漱石氏とは、餘程色彩の變つた世界を、階子段一つ隔てた上と下とに現出せしめて居つた譯である。然しそれがまた後年になつて或點まで似よつた境界に身を置いて共に明治大正の文壇の一人者として立つやうになつたことも興味あることである。
子規居士が此家に居つたのは凡そ一ヶ月位のことであつたかと思ふ。これは最近歸省した時に極堂、霽月等の諸君に聞いた話であるが、その一ケ月ほどの滯在の半ば以上過ぎた頃のことであつたらう、不圖俳句の話が寫生といふことに移つて、是非とも寫生をしなければ新しい俳句は出來ないという居士の主張を明日は實行して見ようといふことになつて、その翌日天氣の好いのを幸に居士は極堂其他の諸君と共に珍らしく戸外に出て、稲の花の咲いて居る東郊を漫歩して石手寺の邊まで歩いて行き、それから又同じ道を引き返して歸つて來た。居士の、
南無大師石手の寺や稲の花
などゝいう句はこの時に出來た句であるさうな。今から見ると寫生々々といい乍ら尚ほその手法は殻を脱しない幼稚なものであるが、とにかく寫生ということに着眼して、それを獎勵皷舞したことは此時代に始まつてゐるのである。それから無事に宿まで歸つて來て極堂君等も皆自分の家に歸つたのであるが、極堂君は晩餐をすましてから晝間の盡きなかつた興をたどりつゝ、また居士の寓居に出掛けて行つたところが、居士は病床に寝たまゝで枕元の痰吐きに澤山咯血をしてゐた。枕頭についてゐるものは上野の未亡人ばかりであつた。居士が低い聲で手招ぎするので極堂君が傍に行つて見ると、それは氷嚢と氷を買つて來て呉れといふのであつた。そこで極堂君は取るものも取り敢へず氷嚢と氷を買つて來たのであつたが、その留守中に大原の叔母君と医者とが來て居つた。その咯血は長くはつゞかなくつて、それから間もなく東京に歸るようになつたのであつた、といふことであつた。
漱石氏がよく又話して居つたことにこういう話がある。
「子規という奴は亂暴な奴だ。僕ところに居る間毎日何を食ふかといふと鰻を食はうといふ。それで殆んど毎日のように鰻を食つたのであるが、歸る時になつて、萬事頼むよ、とか何とか言つた切りで發つてしまつた。その鰻代も僕に拂はせて知らん顔をしてゐた。」斯ういふ話であつた。極堂君の話に、漱石氏は月給を貰つて來た日など、小遣をやろうかと言つて居士の布團の下に若干の紙幣を敷き込んだことなどもあつたさうだ。もつとも東京の新聞社で僅わずかに三、四十圓の給料を貰つていた居士に比べたら、田舎の中學校に居て百圓近い給料を貰つてゐた漱石氏は餘程懐ろ都合の潤澤なものであつたらう。
私は明治三十年の春に歸省した。その時漱石氏をその二番町の寓居に訪問した。其時私の眼には漱石氏よりも寧ろ髪を切つてゐる上野未亡人の方が強く印象された。今から考へてみて其頃は四十前後であつたらうかと思われるが、白粉をつけてゐたのか、それとも地色が白かつたのか、兎に角私の目には白い顔が映つた。漱石氏のところで午飯の御馳走になつた時に、此色の白い髪を切つた未亡人は給仕して呉れた。最近私が松山に歸つてゐる時に次のやうな手紙が案頭に落ちた。
博多には珍しい雪がお正月からふり続いております。きのふからそのために電話も電燈もだめ、電車は一時とまるといふ騒ぎです。松山は如何ですか。けさ一寸新聞で下關までおいでの事を承知いたしましたので急に手紙がさし上げたくなりました。それに二月號のホトヽギスを昨日拜見したものですから。その上一月號の時も申上げたかつた事をうつちやつていますから。
一月號の「兄」では私上野の祖父を思ひ出して一生懸命に拜見いたしました。祖父は以前は何もかも祖母任せの鷹揚な人だつたと思ひますが、祖母を先だて總領息子を亡くして、その上あの伯母に家出をされ、從姉に(あなたが私と一しょに考へていらつしつた)學資を送るやうになつてからは、實に細かく暮して居たやうです。そして自分はしんの出た帶などをしめても月々の學資はちゃんちゃんと送つてゐましたが、その從姉は祖父のしにめにもあはないで、そしてあとになつて少しばかりの(祖父がそんなにまでして手をつけなかつた)財産を外の親類と爭ふたりしました。漸く裁判にだけはならずにすんだやうでしたが、そのお金もすぐ使ひ果して今伯母も從姉も行方不明です。
おはずかしい事を申上げました。いつもお作を拜見しては親類中の御親しみ深い御樣子を心から羨しく思つてゐたものですから、ついついぐちがこぼれました。おゆるし下さいまし。
あの一番町から上つて行くお家に夏目先生がいらつしやつた事は私にとつてはつ耳です。私は上野のはなれにいつから御移りになつたのか何にも覺えておりません。ただ文學士というえらい肩書の中學校の先生が離れにいらつしやるといふ事を子供心に自慢に思つていた丈です。先生はたしか一年近くあの離れに御住居なすつたのですのに、どういう譯か私のあたまには夏から秋まで同居なすつた正岡先生の方がはつきりうつてゐます。――松山のかたゞといふ親しみもしらずしらずあつたのでせうが――夏目先生の事はたゞかあいがつていたゞいたやうだ位しきや思ひ出せません。照葉狂言にも度々たびたびおともしましたが、それもやつぱり正岡先生の方はおめし物から帽子まで覺えてゐますのに(うす色のネルに白縮緬のへこ帶、ヘルメツト帽)夏目先生の方ははつきりしないんです。たゞ一度伯母が袷と羽織を見たてゝさし上げたのは覺えてゐます。それと一度夜二階へお邪魔をしてゐて、眠くなつて母家へ歸らうとしますと、廊下におばけが出るよとおどかされた事とです。それからも一つはお嫁さん探しを覺えてゐます。先生はたぶん戯談でおつしやつたのでせうが祖母や伯母は一生懸命になつて探してゐたようです。そのうち東京でおきまりになつたのが今の奥樣なんでせう。私は伯母がそつと見せてくれた高島田にお振袖のお見合のお寫眞をはじめて千駄木のお邸で奥樣におめにかゝつた時思ひ出しました。
實は千駄木へはじめて御伺ひした時は玄関拂ひを覺悟して居たのです。十年も前に松山で、といふような口上でおめにかゝれるかどうかとおずおずしてゐたのですが、すぐあつて下すつて大きくなつたねといつて下すつた時は嬉しくてたまりませんでした。そして私の姓が變つた事をおきゝになつて、まあよかつた、美術家でなくつても文學趣味のあるお医者さんだからとおつしやつたのにはびつくりいたしました。先生は私が子供の時學校で志望をきかれた時の返事を伯母が笑ひ話にでもしたのをちゃんと覺えていらつしつたものと見えます。松山を御出立の前夜湊町の向井へおともして買つていただいた呉春と応擧と常信との畫譜は今でも持つてをりますが、あのお離れではじめて知つた雜誌の名が帝國文學で、貸していたゞいて讀んだ本が保元平治物語とお伽草紙です。
興にのつて大變ながく書きました。おいそがしい所へすみません。あの二番町の家は今どうなつたことでせう。長塚さんもいつかこちらへお歸りに前を通つてみたとおつしゃつてゐました。あの離れはたしか私たちがひつこしてから、祖父の隠居所にといつて建てたものゝやうです。襖のたて合せのまんなかの木ぎれをもらつておひな樣のこしかけにしたのを覺えています。
ほんとにくだらない事ばかりおゆるしを願ひます。松山にはどれ位御逗留かも存じません。この手紙どこでごらん下さるでせう。
寒さの折からおからだをお大切に願ひます。
よりえ
此手紙をよこした人は本誌の讀者が近づきであるところの「中の川」「嫁ぬすみ」の作者である久保よりえ夫人である。此夫人は此上野未亡人の姪に當る人である。ある時早稲田南町の漱石氏の宅を訪問した時に席上にある一婦人は久保猪之吉博士の令閨として紹介された。そうしてそれが當年漱石氏の下宿してゐた上野未亡人の姪に當る人だと説明された時に、私は未亡人の膝元にちらついていた新蝶々の娘さんを思い出してその人かと思つたのであつたが其は違つていた。文中に在る從姉とあるのがその人であつた。このよりえ夫人の手紙は未亡人の其後をよく物語つている。あの家は今は上野氏の手を離れて他人の有となつているといふ事である。
此三十年の歸省の時、私はしばしば漱石氏を訪問して一緒に道後の温泉に行つたり、俳句を作つたりした。その頃道後の鮒屋ふなやで初めて西洋料理を食はすようになつたというので、漱石氏はその頃學校の同僚で漱石氏の下にあつて英語を教へている何とかいう一人の人と私とを伴つて鮒屋へ行つた。白い皿の上に載せられて出て來た西洋料理は黑い堅い肉であつた。私はまずいと思つて漸く一きれか二きれかを食つたが、漱石氏は忠實にそれを噛かみこなして大概嚥下してしまつた。今一人の英語の先生は關羽のような長い髯を蓄えてゐたが、それもその髯を動かしながら大方食つてしまつた。此先生は金澤の高等學校を卒業したきりの人であるという話であつたが、妙に氣取つたように物を言ふ滑稽味のある人であつた。此人はよく漱石氏の家へ出入してゐるようであつた。この鮒屋の西洋料理を食つた時に、三人は矢張り道後の温泉にも這入つた。着物を脱ぐ時に「赤シャツ」という言葉が漱石氏の口から漏れて兩君は笑つた。それは此先生が赤いシャツを着て居つたからであつたかどうであつたか、はつきり記憶に殘つて居らん。只私が裸になつた時に私の猿股にも赤い筋が這入つていたので漱石氏は驚いたやうな興味のあるような眼をして、
「君のも赤いのか。」と言つたことだけは、はつきりと覺えている。後年「坊つちゃん」の中に赤シャツという言葉の出て來た時にこの時のことを思ひ合わせた。
或日漱石氏は一人で私の家うちの前まで來て、私の机を置いている二階の下に立つて、
「高濱君。」と呼んだ。その頃私の家は玉川町の東端にあつたので、小さい二階は表ての青田も東の山も見える樣に往來に面して建つてゐた。私は障子をあけて下をのぞくとそこに西洋手拭をさげてゐる漱石氏が立つてゐて、また道後の温泉に行かんかと言つた。そこで一緒に出かけてゆつくり温泉にひたつて二人は手拭を提げて野道を松山に歸つたのであつたが、その歸り道に二人は神仙體の俳句を作ろうなどゝ言つて彼れ一句、これ一句、春風駘蕩たる野道をとぼとぼと歩きながら句を拾うのであつた。この神仙體の句はその後村上霽月君にも勸めて、出來上つた三人の句を雜誌めざまし草ぐさに出したことなどがあつた。
引用・参照・底本
『漱石氏と私』高濱清著 大正七年一月三十一日發行 書店アルス
(國立國會図書館デジタルコレクション)
序
漱石氏と私との交遊は疎きがごとくして親しく、親しきが如くして疎きものありたり。その邊を十分に描けば面白かるべきも、本篇は氏の書簡を主なる材料として唯追憶の一端をしるしたるのみ。氏が文壇に出づるに至れる當時の事情は、略々此の書によりて想察し得可し。
大正七年正月七日
ほとゝぎす發行所にて
高濱虚子
永き日や欠伸うつして別れ行く === 漱石氏筆
漱石氏と私
(15-35頁)
二
明治二十九年の夏に子規居士が從軍中咯血をして神戸、須磨と轉々療養をした揚句松山に歸省したのはその年の秋であつた。その叔父君にあたる大原氏の家うちに泊つたのは一、二日のことで直ぐ二番町の横町にある漱石氏の寓居に引き移つた。これより前、漱石氏は一番町の裁判所裏の古道具屋を引き払つて、この二番町の横町に新らしい家を見出したのであつた。そこは上野という人の持家であつて、その頃四十位の一人の未亡人が若い娘さんと共に裏座敷を人に貸して素人下宿を営んでいるのであつた。裏座敷というのは六畳か八畳かの座敷が二階と下に一間ずつある位の家であつて漱石氏はその二間を一人で占領していたのであるが、子規居士が來ると決まつてから自分は二階の方に引き移り、下は子規居士に明け渡したのであつた。
私はその當時の實境を目撃したわけではないが、以前子規居士から聞いた話や、最近國へ歸つて極堂、霽月らの諸君から聞いた話やを綜合して見ると、大體その時の模樣の想像はつくのである。子規居士は須磨の保養院などにいた時と同じく蒲團は畳の上に敷き流しにしておいてくたびれるとその上に横はり、氣持がいゝと蒲団の上に起き上つたり、緣ばな位までは出たりなどして健康の回復を待ちつゝあつたのであらう。それから須磨の保養院に居る頃から筆を執りつゝあつた「俳人蕪村」の稿を纘ぎ、更に「俳諧大要」の稿を起すようになつたのであつた。子規居士が歸つたと聞いてから、折節歸省中であつた下村爲山君を中心として俳句の研究をしつゝあつた中村愛松あいしょう、野間叟柳、伴狸伴、大島梅屋の小學教員團體が早速居士の病床につめかけて俳句の話を聞くことになつた。居士は從軍の結果が一層健康を損じ、最早一圖に俳句にたずさはるよりほか、仕方がないとあきらめをつけ、さうでなくつても根柢から此短い詩の研究に深い注意を拂つてゐたのが、更に勇猛心を振ひ興して斯道に力を盡さうと考へていた矢先であつたので、それ等の教員團體、並びに舊友であるところの柳原極堂、村上霽月、御手洗不迷等の諸君を病床に引きつけて、殆んど休む間もなしに句作をしたり批評をしたりしたものらしい。その間漱石氏は主として二階にあつて、朝起きると洋服を着て學校に出かけ、歸つて來ると洋服を脱いで翌日の講義の下調べをして、二階から下りて來ることは少なかつたが、それでも時々は下りて來てそれらの俳人諸君の間に交つて一緒に句作することもあつた。子規居士はやはり他の諸君の句の上に○をつけるのと同じように漱石氏の句の上にも○をつけた。只他の人は「お前」とか「あし」とか松山言葉を使つて呼び合つてゐる中に、漱石氏と居士との間だけには君とか僕とかいふ言葉を用ひていた位の相違であつた。漱石氏は是等の松山言葉を聞くことや、足を投げ出したり頬杖をついたりして無作法な樣子をして句作に耽つている一座の樣子を流し目に見て餘いゝ心持もしなかつたらうが、その病友の病を忘れてゐるかの如き奮闘的な態度には敬意を払つてゐたに相違ない。殊に漱石氏は子規居士が親分らしい態度をして無造作に人々の句の上に○をつけたり批評を加へたりするのを、感服と驚きと可笑味とを混ぜたような眼つきをして見てゐたに相違ない。殊に又自分の句の上に無造作に○がついたり直が這入つたりするのを一層不思議さうな眼でながめていたに相違ない。
「子規といふ男は何でも自分が先生のような積りで居る男であつた。俳句を見せると直ぐそれを直したり圏點をつけたりする。それはいゝにしたところで僕が漢詩を作つて見せたところが、直ぐ又筆をとつてそれを直したり、圏点をつけたりして返した。それで今度は英文を綴つて見せたところが、奴さんこれだけは仕方がないものだから Very good と書いて返した。」と言つてその後よく人に話して笑つてゐた。
後年になつて漱石氏の鋭い方面はその鋒先をだんだんと嚢の外に表わし始めたが、その頃の――殊に若年であつた私の目に映じた――漱石氏は非常に温厚な紳士的態度の長者らしい風格の人のように思はれた。自然子規居士の親分氣質な動作に對しても別に反抗するような態度もなく、俳句の如きは愛松、極堂、霽月等の諸君に伍して子規居士の傘下に集まつた一人として別に意に介する所もなかつたのであらう。のみならず、この病友をいつくしみ憐れむような友情と、その親分然たる態度に七分の同感と三分の滑稽味を見出す興味とで、格別厭な心持もしないでその階下に湧き出した一箇の世界を眺めてゐたものであらう。そうして朝暮出入してゐる愛松、極堂らの諸君とは軌道を異にして、多くの時間は二階に閉籠つて學校の先生としての忠實なる準備と英文學者としての眞面目な修養とに力を注いでゐたのである。後年「坊つちやん」の一篇が出るやうになつてから、此松山中學時代の漱石氏の不平は俄かに明るみに取り出された傾きがあるが、當時の氏にはたとひそれらの不愉快な心持が内心にあつたとしても、それ等の不愉快には打勝ちつゝ、どこまでも眞面目に、學者として教師として進んで行く考であつたことは間違ひない。大學を中途で退學して新聞社に這入つて不治の病氣になつて居た子規居士と、眞直に大學を出て中學校の先生としていそしみつゝあつた漱石氏とは、餘程色彩の變つた世界を、階子段一つ隔てた上と下とに現出せしめて居つた譯である。然しそれがまた後年になつて或點まで似よつた境界に身を置いて共に明治大正の文壇の一人者として立つやうになつたことも興味あることである。
子規居士が此家に居つたのは凡そ一ヶ月位のことであつたかと思ふ。これは最近歸省した時に極堂、霽月等の諸君に聞いた話であるが、その一ケ月ほどの滯在の半ば以上過ぎた頃のことであつたらう、不圖俳句の話が寫生といふことに移つて、是非とも寫生をしなければ新しい俳句は出來ないという居士の主張を明日は實行して見ようといふことになつて、その翌日天氣の好いのを幸に居士は極堂其他の諸君と共に珍らしく戸外に出て、稲の花の咲いて居る東郊を漫歩して石手寺の邊まで歩いて行き、それから又同じ道を引き返して歸つて來た。居士の、
南無大師石手の寺や稲の花
などゝいう句はこの時に出來た句であるさうな。今から見ると寫生々々といい乍ら尚ほその手法は殻を脱しない幼稚なものであるが、とにかく寫生ということに着眼して、それを獎勵皷舞したことは此時代に始まつてゐるのである。それから無事に宿まで歸つて來て極堂君等も皆自分の家に歸つたのであるが、極堂君は晩餐をすましてから晝間の盡きなかつた興をたどりつゝ、また居士の寓居に出掛けて行つたところが、居士は病床に寝たまゝで枕元の痰吐きに澤山咯血をしてゐた。枕頭についてゐるものは上野の未亡人ばかりであつた。居士が低い聲で手招ぎするので極堂君が傍に行つて見ると、それは氷嚢と氷を買つて來て呉れといふのであつた。そこで極堂君は取るものも取り敢へず氷嚢と氷を買つて來たのであつたが、その留守中に大原の叔母君と医者とが來て居つた。その咯血は長くはつゞかなくつて、それから間もなく東京に歸るようになつたのであつた、といふことであつた。
漱石氏がよく又話して居つたことにこういう話がある。
「子規という奴は亂暴な奴だ。僕ところに居る間毎日何を食ふかといふと鰻を食はうといふ。それで殆んど毎日のように鰻を食つたのであるが、歸る時になつて、萬事頼むよ、とか何とか言つた切りで發つてしまつた。その鰻代も僕に拂はせて知らん顔をしてゐた。」斯ういふ話であつた。極堂君の話に、漱石氏は月給を貰つて來た日など、小遣をやろうかと言つて居士の布團の下に若干の紙幣を敷き込んだことなどもあつたさうだ。もつとも東京の新聞社で僅わずかに三、四十圓の給料を貰つていた居士に比べたら、田舎の中學校に居て百圓近い給料を貰つてゐた漱石氏は餘程懐ろ都合の潤澤なものであつたらう。
私は明治三十年の春に歸省した。その時漱石氏をその二番町の寓居に訪問した。其時私の眼には漱石氏よりも寧ろ髪を切つてゐる上野未亡人の方が強く印象された。今から考へてみて其頃は四十前後であつたらうかと思われるが、白粉をつけてゐたのか、それとも地色が白かつたのか、兎に角私の目には白い顔が映つた。漱石氏のところで午飯の御馳走になつた時に、此色の白い髪を切つた未亡人は給仕して呉れた。最近私が松山に歸つてゐる時に次のやうな手紙が案頭に落ちた。
博多には珍しい雪がお正月からふり続いております。きのふからそのために電話も電燈もだめ、電車は一時とまるといふ騒ぎです。松山は如何ですか。けさ一寸新聞で下關までおいでの事を承知いたしましたので急に手紙がさし上げたくなりました。それに二月號のホトヽギスを昨日拜見したものですから。その上一月號の時も申上げたかつた事をうつちやつていますから。
一月號の「兄」では私上野の祖父を思ひ出して一生懸命に拜見いたしました。祖父は以前は何もかも祖母任せの鷹揚な人だつたと思ひますが、祖母を先だて總領息子を亡くして、その上あの伯母に家出をされ、從姉に(あなたが私と一しょに考へていらつしつた)學資を送るやうになつてからは、實に細かく暮して居たやうです。そして自分はしんの出た帶などをしめても月々の學資はちゃんちゃんと送つてゐましたが、その從姉は祖父のしにめにもあはないで、そしてあとになつて少しばかりの(祖父がそんなにまでして手をつけなかつた)財産を外の親類と爭ふたりしました。漸く裁判にだけはならずにすんだやうでしたが、そのお金もすぐ使ひ果して今伯母も從姉も行方不明です。
おはずかしい事を申上げました。いつもお作を拜見しては親類中の御親しみ深い御樣子を心から羨しく思つてゐたものですから、ついついぐちがこぼれました。おゆるし下さいまし。
あの一番町から上つて行くお家に夏目先生がいらつしやつた事は私にとつてはつ耳です。私は上野のはなれにいつから御移りになつたのか何にも覺えておりません。ただ文學士というえらい肩書の中學校の先生が離れにいらつしやるといふ事を子供心に自慢に思つていた丈です。先生はたしか一年近くあの離れに御住居なすつたのですのに、どういう譯か私のあたまには夏から秋まで同居なすつた正岡先生の方がはつきりうつてゐます。――松山のかたゞといふ親しみもしらずしらずあつたのでせうが――夏目先生の事はたゞかあいがつていたゞいたやうだ位しきや思ひ出せません。照葉狂言にも度々たびたびおともしましたが、それもやつぱり正岡先生の方はおめし物から帽子まで覺えてゐますのに(うす色のネルに白縮緬のへこ帶、ヘルメツト帽)夏目先生の方ははつきりしないんです。たゞ一度伯母が袷と羽織を見たてゝさし上げたのは覺えてゐます。それと一度夜二階へお邪魔をしてゐて、眠くなつて母家へ歸らうとしますと、廊下におばけが出るよとおどかされた事とです。それからも一つはお嫁さん探しを覺えてゐます。先生はたぶん戯談でおつしやつたのでせうが祖母や伯母は一生懸命になつて探してゐたようです。そのうち東京でおきまりになつたのが今の奥樣なんでせう。私は伯母がそつと見せてくれた高島田にお振袖のお見合のお寫眞をはじめて千駄木のお邸で奥樣におめにかゝつた時思ひ出しました。
實は千駄木へはじめて御伺ひした時は玄関拂ひを覺悟して居たのです。十年も前に松山で、といふような口上でおめにかゝれるかどうかとおずおずしてゐたのですが、すぐあつて下すつて大きくなつたねといつて下すつた時は嬉しくてたまりませんでした。そして私の姓が變つた事をおきゝになつて、まあよかつた、美術家でなくつても文學趣味のあるお医者さんだからとおつしやつたのにはびつくりいたしました。先生は私が子供の時學校で志望をきかれた時の返事を伯母が笑ひ話にでもしたのをちゃんと覺えていらつしつたものと見えます。松山を御出立の前夜湊町の向井へおともして買つていただいた呉春と応擧と常信との畫譜は今でも持つてをりますが、あのお離れではじめて知つた雜誌の名が帝國文學で、貸していたゞいて讀んだ本が保元平治物語とお伽草紙です。
興にのつて大變ながく書きました。おいそがしい所へすみません。あの二番町の家は今どうなつたことでせう。長塚さんもいつかこちらへお歸りに前を通つてみたとおつしゃつてゐました。あの離れはたしか私たちがひつこしてから、祖父の隠居所にといつて建てたものゝやうです。襖のたて合せのまんなかの木ぎれをもらつておひな樣のこしかけにしたのを覺えています。
ほんとにくだらない事ばかりおゆるしを願ひます。松山にはどれ位御逗留かも存じません。この手紙どこでごらん下さるでせう。
寒さの折からおからだをお大切に願ひます。
よりえ
此手紙をよこした人は本誌の讀者が近づきであるところの「中の川」「嫁ぬすみ」の作者である久保よりえ夫人である。此夫人は此上野未亡人の姪に當る人である。ある時早稲田南町の漱石氏の宅を訪問した時に席上にある一婦人は久保猪之吉博士の令閨として紹介された。そうしてそれが當年漱石氏の下宿してゐた上野未亡人の姪に當る人だと説明された時に、私は未亡人の膝元にちらついていた新蝶々の娘さんを思い出してその人かと思つたのであつたが其は違つていた。文中に在る從姉とあるのがその人であつた。このよりえ夫人の手紙は未亡人の其後をよく物語つている。あの家は今は上野氏の手を離れて他人の有となつているといふ事である。
此三十年の歸省の時、私はしばしば漱石氏を訪問して一緒に道後の温泉に行つたり、俳句を作つたりした。その頃道後の鮒屋ふなやで初めて西洋料理を食はすようになつたというので、漱石氏はその頃學校の同僚で漱石氏の下にあつて英語を教へている何とかいう一人の人と私とを伴つて鮒屋へ行つた。白い皿の上に載せられて出て來た西洋料理は黑い堅い肉であつた。私はまずいと思つて漸く一きれか二きれかを食つたが、漱石氏は忠實にそれを噛かみこなして大概嚥下してしまつた。今一人の英語の先生は關羽のような長い髯を蓄えてゐたが、それもその髯を動かしながら大方食つてしまつた。此先生は金澤の高等學校を卒業したきりの人であるという話であつたが、妙に氣取つたように物を言ふ滑稽味のある人であつた。此人はよく漱石氏の家へ出入してゐるようであつた。この鮒屋の西洋料理を食つた時に、三人は矢張り道後の温泉にも這入つた。着物を脱ぐ時に「赤シャツ」という言葉が漱石氏の口から漏れて兩君は笑つた。それは此先生が赤いシャツを着て居つたからであつたかどうであつたか、はつきり記憶に殘つて居らん。只私が裸になつた時に私の猿股にも赤い筋が這入つていたので漱石氏は驚いたやうな興味のあるような眼をして、
「君のも赤いのか。」と言つたことだけは、はつきりと覺えている。後年「坊つちゃん」の中に赤シャツという言葉の出て來た時にこの時のことを思ひ合わせた。
或日漱石氏は一人で私の家うちの前まで來て、私の机を置いている二階の下に立つて、
「高濱君。」と呼んだ。その頃私の家は玉川町の東端にあつたので、小さい二階は表ての青田も東の山も見える樣に往來に面して建つてゐた。私は障子をあけて下をのぞくとそこに西洋手拭をさげてゐる漱石氏が立つてゐて、また道後の温泉に行かんかと言つた。そこで一緒に出かけてゆつくり温泉にひたつて二人は手拭を提げて野道を松山に歸つたのであつたが、その歸り道に二人は神仙體の俳句を作ろうなどゝ言つて彼れ一句、これ一句、春風駘蕩たる野道をとぼとぼと歩きながら句を拾うのであつた。この神仙體の句はその後村上霽月君にも勸めて、出來上つた三人の句を雜誌めざまし草ぐさに出したことなどがあつた。
引用・参照・底本
『漱石氏と私』高濱清著 大正七年一月三十一日發行 書店アルス
(國立國會図書館デジタルコレクション)